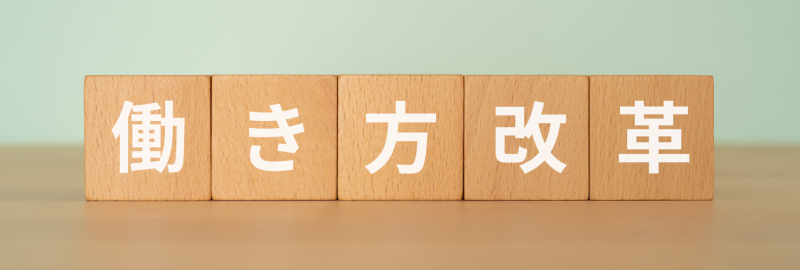
1. 当直の定義と宿日直許可
医師の働き方改革において、当直の取り扱いは重要な課題です。医師の労働時間には上限規制があり、原則として当直業務も例外ではありません。しかし、一定の条件を満たす場合には、労働基準法上の労働時間規制の適用除外が認められることがあります。これが「宿日直許可」です。簡単に言うと、通常であれば労働時間とみなされる宿日直勤務でも、この許可を得ることで、時間外労働の制限や割増賃金の支払いなどが適用されなくなることがあります。
なお、「宿日直許可」は病院全体に対して取得するものではありません。そのため、病院として書類を提出しますが、「特定の診療科のみ許可が下りる」「特定の時間帯のみ許可が下りる」といったケースがあります。まずはどの診療科・どの時間帯で許可が取得できているかを確認してください。宿日直許可を得ている医療機関は、今後の医師採用において有利になる可能性が高く、労働時間の上限規制からも除外されるため、可能な限り取得しておくことが推奨されます。
Q: 宿日直許可申請について、麻酔科などはオペが無ければ寝当直になり、オペがあれば夜勤相当になります。 この場合は宿日直許可は申請すべきでしょうか?
A: 時間帯や業務内容によっては、条件付きで許可が下りる場合があるようです。 労基署または都道府県の医療勤務環境改善支援センターへご相談ください。
2. 当直時間とインターバル規制
医師の働き方改革では、以下の2種類の勤務間インターバル規制が設けられています。
- 2.1 インターバル規制の種類
- ①始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間(15時間の連続勤務時間制限)
- ②始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間(28時間の連続勤務時間制限)
- 2.2 当直時間と規制の適用 当直時間が15時間以内であれば①の規制が適用され、宿日直許可を取得することで、勤務間インターバル規制の適用が変わる場合があります。
3. 当直許可の条件と例外
- 3.1 当直許可の原則 基本的には、宿日直許可は当直週1回、日直月1回を限度として認められます。
- 3.2 当直許可の例外 ただし、医師確保が困難な地域や、特殊なスキルを要する医師が必要な場合など、例外的に認められる場合もあります。
Q: 宿日直許可について、申請が下りる条件に当直週1回の宿日直とありますが代わりの医師がおりません。 どうしたらよいでしょうか?
A: 基本条件は当直週1回、日直月1回ですが医師確保が困難な地域や特殊なスキルを必要とする場合など、例外的に認められている場合もございます。 現状を含めて一度労基署にご相談をお勧めいたします。
- 3.3 当直時間と労働時間の扱い 金曜日の夜から土曜日の日直までは労働時間対象外でも、土曜日の夜以降は労働時間となる可能性や、へき地等で常勤医師が少なく、どうしても医師を確保できないといった事情が認められれば、連続した日直(月2回)が許可される場合もあります。
- 3.4 連続当直の許可 連続当直については、月4回程度まで認められる場合があり、例えば、月曜日と火曜日の連続当直でも翌週が免除されれば許可されたケースもあります。
Q: 宿日直許可を取得する条件として当直週1回までの制限がありますが、原則6日間の間隔が開かないといけないのでしょうか?
A: 月4回くらいのイメージです。 月火の連続当直であっても、翌週が免除されていれば許可されたケースもあります。
- 3.5 当直業務と通常勤務の混在 当直業務と通常勤務が混在する場合は、労基署への確認が必要です。
Q: 週2回以上当直に入る医師が複数いる場合、必ず週1回の勤務にしてからでないと申請はだせないのですか。
A: 基本的に宿日直許可が認められるのは当直週1回、日直月1回ですが「そのうちの1回のみ」という条件で宿日直許可を取得することが可能です。 ただし、残りの日付はすべて宿日直許可が取れていない時間帯になってしまうため、時間外労働時間としてのカウントが必要ですのでご注意ください。
4. 宿日直許可の取得と時間外労働
- 4.1 宿日直許可の条件付き取得 「そのうちの1回のみ」という条件付きで宿日直許可を取得することも可能です。
Q: 週2回以上当直に入る医師が複数いる場合、必ず週1回の勤務にしてからでないと申請はだせないのですか。
A: 基本的に宿日直許可が認められるのは当直週1回、日直月1回ですが「そのうちの1回のみ」という条件で宿日直許可を取得することが可能です。 ただし、残りの日付はすべて宿日直許可が取れていない時間帯になってしまうため、時間外労働時間としてのカウントが必要ですのでご注意ください。
- 4.2 許可時間外の労働時間の扱い ただし、許可を得ている時間帯以外は、時間外労働時間としてカウントする必要があるため、注意が必要です。
5. 当直手当の取り扱い
- 5.1 当直手当の記載 宿日直手当は、賃金規程または雇用契約書のいずれかに記載する必要があります。
Q: 雇用契約書に日当直手当も明記した方が良いでしょうか? 現状では変動もあるので、金額を明記したくないという事情もあります。 (尚、賃金規定にも医師の手当は載せていません。)
A: 賃金規程に記載があれば、「日当直手当 就業規則による」と記載すればいいですが、賃金規程に記載がないのであれば、雇用契約書には記載すべきです。 変動も含めて賃金規程に記載する(もしくは医師賃金規程を作成する)か、可能な範囲で雇用契約書に記載すべきかと思います(例「日当直手当 〇〇〇円~)。 どうしても記載が難しいようであれば「日当直手当 別途定める」とするしかないかと思います。
- 5.2 当直手当の記載方法 手当額の変動も含めて賃金規程に記載するか、可能な範囲で雇用契約書に記載することが望ましいです。
- 5.3 日直時間の定義 日直と定義される時間が短すぎる(4時間以内など)場合、労基署に日直と認めてもらえない事例があるため、注意が必要です。
Q: 土曜日の午前中は診療があり、午後から日直となります。 この場合は診療が終わってから当日の当直が始まるまでを日直と定義すればよいのでしょうか?
A: 日直と定義される時間が短すぎる(4時間以内)場合、労基署に日直と認めてもらえない事例が発生しております。 通常勤務として取り扱う、もしくは当直として定義するなど、労基署によって対応が違ってまいりますので管轄の労基署にお問合せください。
6. 当直時間外手当の算出
- 6.1 時間外手当の算出方法 時間外手当を算出する際、統計データを利用したり、勤務時間が少ない場合は算出母数に含めない等の事例があります。
Q: 最低手当額を算出する際、医師の日額の賃金の算出が必要ですが、当直しか入っていない医師の日額はどのように計算するのでしょうか?
A: 労基署によって対応が変わってまいりますが一例として、
・統計データを利用し日額を算出する
・(勤務が少ない場合)そもそも算出母数に含めない
などの事例がございます。宿日直に入る常勤医師と非常勤医師の人数によっても変わってまいりますので、管轄の労基署にお問い合わせください。
Q: 宿日直手当の最低額を算出するにあたり、当院で当直や日直のみしか入っていない場合は常勤医師のみで基準額を計算とお伺いしましたが、常勤医師が1名しかおらずほとんどの当直日直を非常勤で賄っております。 その場合も常勤医師の日額を基本として問題ないでしょうか?
A: 最終的には労基署の判断となりますが、「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金」を用いて日額を算出したケースもあります。
- 6.2 算出方法の確認 算出方法が常勤医師と非常勤医師の人数構成等によっても異なるため、管轄の労基署に確認することが重要です。
Q: 当直時間帯に10件ほど医師の対応が発生する場合がありますが、この状態だと宿日直許可の取得は難しいでしょうか?
A: 10件近くの対応があっても許可が下りたケースがございます。 ポイントとしては「対応内容が軽度かつ短時間かなものであるかどうか」という点です。 いずれにしろ許可判断のためには、1件当たりの対応に要した時間、件数、処置内容の資料が必要となりますのでご用意の上、管轄の労基署にご相談ください。
7. 当直回数の制限と給与
- 7.1 当直回数の制限 常勤医師、非常勤医師に関わらず「週1回まで」の当直制限が適用されます。
Q: 常勤医師2名のコマ以外はすべて外部非常勤医師が当直勤務しておりますが、週2回以上当直に入る医師も複数名おります。 このような場合でも「当院は宿直許可申請済なので労働カウントされない」と案内してよいのか、あるいは週2回以上勤務する医師に対しては「労働カウントされる」と案内すべきでしょうか?
A: 常勤医師、非常勤医師関係なく「週1回まで」の条件が適用されます。 よって、
・週1回にシフトを調整する
・週2回のままだが、うち1回分だけ通常勤務とし労働カウントとする
のどちらかの方針にて宿日直許可を取得することになります。
- 7.2 当直回数制限時の給与への配慮 当直回数を制限する場合、勤務が減る医師に対して、給与を減らさない、または減らしても少額にとどめる対応をしている医療機関が多いです。
Q: 宿日直許可申請を行うため、現在当直週2回勤務している医師を週1回に調整する必要がある認識です。 その際、給与が減ることに対して他病院ではどのように対処されているのでしょうか?
A: 弊社でお伺いした事例では、勤務が減ったとしても給与を減らさないor減らしたとしても少額に抑える対応をしている病院が非常に多いです。
8. 当直明けの勤務と有給休暇
- 8.1 A水準病院の対応 A水準病院の場合、当直明けに年次有給休暇を取得することは、病院の判断に委ねられています。
Q: 当院では当直翌日を休みにする際、有給を消化するルールを運用しております。 2024年4月以降、運用を継続しても問題ないでしょうか?
A:
①A水準の場合は、努力義務であるため病院の判断で構いません。
②BC水準の場合、宿日直許可の有無で対応は変わってくるかと思います。 宿日直許可がある場合、宿直は労働時間とはなりませんので、その宿直時間を休息時間として考えることができます。
そのため、次の日の日勤が勤務予定で年次有給休暇を取得することは問題ありません。
宿直許可がない場合、宿直業務も労働時間とみなされ、始業から 46 時間以内に18 時間の連続した休息時間(28 時間の連続勤務時間制限)が必要になります。
厚生労働省によると「9時間又は 18 時間の連続した休息時間は、事前に勤務シフト表等で予定されたものであることが原則となる」とあるため、勤務予定日にのみ取得できる年次有給休暇をあてることは難しいと思います。 上記の大前提のルールを踏まえ、医師の当直時の勤務状況(忙しさ)を踏まえて病院としての有給取得方針を決定いただければと思います。
- 8.2 B・C水準病院の対応 B・C水準病院の場合、宿日直許可の有無によって対応が変わります。
- 許可がある場合:宿直は労働時間とみなされないため、明けに年次有給休暇を取得することは問題ありません。
- 許可がない場合:宿直業務も労働時間とみなされ、始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保する必要があり、有給休暇の取得が難しい場合があります。
- 8.3 当直明けの勤務への配慮 当直明けの勤務への配慮として、明け日を研究日とする、早退可能とするなどの対応をしている事例があります。
Q: 宿日直許可が取れた当直の明けは、その後通常勤務ができるという認識で問題ないでしょうか?
また、宿日直許可明けの勤務対応について、他病院での事例をお伺いしたいです。
A: 宿日直許可が下りていれば労働とはカウントされないため、明けでの通常勤務は可能です。 ただし、以下のような対応をされている病院もいらっしゃいます。
・ 明けに2時間の公休を付与し、月内であればどこでも使えるようにしている
・ 明けの次の日を研究日とし、勤務するかどうかの裁量を医師に与えている
・ 明け後の勤務日は早退を可能にする(事前申告)
当直中の業務量により明けの対応が異なってくるかと思いますが、ご参考になさってください。
9. 固定残業代と当直手当
- 9.1 固定残業代の支払い 固定残業代制を導入している場合、固定残業代として支払われている時間を超えて労働した時間については、時間給×1.25で計算した時間外手当を支払う必要があります。
Q: 別途残業代を支給する場合、労働条件に以下のような文言を加える予定ですが問題ないでしょうか? “所定外勤務40時間相当分を超過した場合、医師就業規則別表に定める当直手当や緊急対応手当等の基準外手当の支給状況を勘案して別途追加で支給する場合がある。”
A: 「支給する場合がある」の表現がNGになる可能性があります。「支給する場合がある」ではなく、固定残業部分を超えた時間については、必ず時間給×1.25を支払う必要があります。ので、「別途追加で支給する」の表現が正しいです。
- 9.2 支払いに関する適切な表現 「支給する場合がある」ではなく、「別途追加で支給する」等の、支払いを明確にする表現が適切です。
10. 当直医師の募集
- 10.1 当直のみの募集 宿直時間帯のみの求人を出している医療機関も多く、宿直のみの医師募集も可能です。
Q: 働き方改革の影響で、宿直の時間帯の人員が不足する見込みです。 当直の時間帯のみの求人を出すことは可能でしょうか?
A: 可能です。 多くの病院様が宿直時間帯のみの求人を出していただいております。 宿直のみの求人作成についてご不明点ございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。
11. 勤務時間と休憩時間
- 11.1 勤務時間と労働時間の考え方 土曜日の日勤後から当直に入り、翌日の日直も行うという勤務形態の場合、宿日直許可が取得できている時間帯は労働時間にカウントされません。
Q: 下記のような働き方をしている医師がいるのですが、インターバルの確保は必要でしょうか? 土曜日:朝8時~14時まで外来(通常労働)/14時~翌朝8時まで当直 日曜日:朝8時~18時まで日直 ちなみに、土曜日の 14 時~翌朝 8 時までは宿日直許可が取得できております。
A: こちらの場合、通常労働となるのは土曜日の 8 時~14 時と、日曜日の 8 時~18 時となります。 宿日直許可が取得できている土曜日の 14 時~翌朝日曜日の 8 時までは労働時間にカウントされないため、24 時間以内の 9 時間の連続した休息が取れている状態となっております。 インターバルのルールを満たしていますので特段問題ありません。
- 11.2 休憩時間の定義 休憩時間は、労働者が「使用者の指揮命令下に置かれていない」状態であることが必要です。
Q: 週1回での宿日直許可が取れている場合、週2回目以降の勤務は通常勤務の扱いとなる認識です。 しかし、当院はほぼ寝当直で勤務がない為、宿直勤務開始の 17 時~18 時と、宿直明け前 1 時間のみを勤務としてみなすことは可能でしょうか?
A: 例え実質的な労働(作業)がなかったとしても、病院にいることが必須とされ、使用者の指揮命令下に置かれている場合は宿直の始まりから終わりまでの全時間帯が労働となります。
12. 当直と労働時間の関係
- 12.1 許可のない当直の時間 許可がない当直の場合、自己研鑽時間も労働時間となる可能性があります。
Q: 非常勤医師が当直中に空き時間やコールに呼ばれない時間で、常勤先での学会準備等、いわゆる自己研鑽していた場合の取り扱いはどうなりますでしょうか?宿日直許可が取れている当直中はそもそももともと労働時間ではないので、研鑽でも何してても支払い金額は変わらないという認識で間違いないでしょうか?
A: 宿日直許可が取れている当直中はご認識のとおりです。 宿日直許可が取れていない当直中の場合、自己研鑽であっても労働時間になる可能性が高いと考えられます。 労働時間とならない自己研鑽の場合は、「労働から離れることが保障されている状態で行われている」必要があります。 宿日直許可がない当直は「所定内労働時間」であり、呼ばれたらすぐに業務に従事することが求められていることから、所定労働時間中の自己研鑽の時間を給与が発生しないように扱うのは難しかと思います。
Q: 非常勤先にて当直中に常勤先の学会準備などをしている場合、非常勤先では特に管理しなくてよい認識ですが相違ないでしょうか?
A: 管理しなくてもよいというより、所定労働時間中の自己啓発は労働時間から除くことは難しいので、始業時間から終業時間までを労働時間として正しく労働時間管理していれば、所定労働時間中に何をしていても構わないという考え方で良いかと思います。
13. その他
- 13.1 非常勤医師の当直 非常勤医師の当直についても、常勤医師と同様に週1回までの制限が適用されます。
Q: 常勤医師2名のコマ以外はすべて外部非常勤医師が当直勤務しておりますが、週2回以上当直に入る医師も複数名おります。 このような場合でも「当院は宿直許可申請済なので労働カウントされない」と案内してよいのか、あるいは週2回以上勤務する医師に対しては「労働カウントされる」と案内すべきでしょうか?
A: 常勤医師、非常勤医師関係なく「週1回まで」の条件が適用されます。 よって、
・週1回にシフトを調整する
・週2回のままだが、うち1回分だけ通常勤務とし労働カウントとする
のどちらかの方針にて宿日直許可を取得することになります。
- 13.2 複数の医療機関での当直 医師が複数の医療機関で当直を行う場合、各事業場ごとに週1回の制限が適用されます。
Q: 1つの医療機関において、1人の医師が宿日直に従事できるのは「当直週1回、日直月1回」とお聞きしました、医師が複数の事業場で宿日直に従事する場合、各事業場ごとに「当直週1回、日直月1回」宿日直業務に従事できるのでしょうか?
A: 以前は、本業副業先を通算して宿直週1回、日直月1回という指導がされることもありましたが、『医療機関の宿日直許可申請に関するFAQより』において「宿日直許可の回数の限度(別は、医療機関ごと(本務先と兼業先それぞれ)で認められた回数を示していますので、医療機関ごとに認められた回数の範囲内で宿日直許可のある業務に従事することが可能です。」とありますので、各事業場ごとに限度回数以内であれば従事可能かと思います。
- 13.3 宿日直許可時間と勤務間インターバル 宿日直許可のある宿日直に従事した時間を「連続した9時間の勤務間インターバル」と扱うことができるのは、9時間以上の連続した宿日直を行った場合に限られます。
Q: 常勤で 8:30~17:00 の日勤 非常勤で 17:30~8:00 の当直 という勤務をしたい医師がおります。 非常勤先では 23:00~翌 5:00 迄は宿日直許可取得済みです。 8:30~17:00 に常勤先勤務 17:30~17:30 で移動 17:30~翌日 8:00 で非常勤勤務 8:00~8:30 で移動 8:30~17:00 で常勤先勤務 上記のスケジュールで勤務されたいとのことなのですが、 連続した休息が宿日直許可取得時間の 6 時間しかありません。 勤務間インターバルを考えた場合、 46 時間の間に連続した 18 時間の連続した休息を取る必要があると思いますが、 この場合、当直明けに常勤先で終日勤務はできず、代償休息の付与や勤務開始時間の後ろ倒し等が必要になりそうでしょうか?
A: 宿日直許可のある宿日直に従事した時間を「連続した9時間の勤務間インターバル」と扱うことができるのは、9時間以上の連続した宿日直を行った場合のみで、9時間未満の宿日直と休息時間を足して連続した9時間の勤務間インターバルを確保したこととすることはできません。 今回のケースは宿日直許可のある宿直に従事する時間が6時間であるため、その時間を休息時間と考えることはできません。 以下のどちらかの方法で勤務間インターバルを確保する必要があります。
・ 8時30分から24時間以内に宿直の6時間とは別に連続した 9 時間の休息を確保
・ 8時30分から 46 時間以内に 18 時間の休息を確保
そのため、宿直明けに常勤先での終日勤務はできず、12 時半までの勤務のシフトとする必要があります(46 時間以内に 18 時間の休息を確保するため)。
- 13.10 経営者の医師の当直勤務 会社経営をしている医師が病院で当直する場合、経営者としての労働時間は通算しませんが、病院での当直は労働時間としてカウントする必要があります。
Q: 会社経営をされている医師が週 2 日(平日)当院で当直されております。 本来、週 1 日しか勤務出来ませんが、この医師については企業経営者であり労働時間として通算する必要のない医師と考えますので週 2 日勤務は可能と判断しております。 この見解に誤りはございませんか?
A: 会社経営をされている場合、その会社での労働時間は通算する必要はありませんが、当院では、一労働者です。 当院においては労働者として扱う必要があるため、当直についても許可の範囲(週 1 日)内で行うべきだと考えます。
- 13.11 当直体制から夜勤体制への移行 働き方改革の流れで、当直体制から夜勤体制への切り替えを検討する医療機関もあります。夜勤体制は勤務時間が明確になり、医師の負担軽減や効率的な診療に繋がる可能性がある一方で、人員確保が難しいなどの注意点があります。
Q: 働き方改革を受けて、当直体制から夜勤体制への切り替えを検討しております。 メリットや注意点を教えてください。
A: 夜勤体制では勤務時間が明確になり、プライベートとのバランスを取りやすくなります。 また、一人当たりの負担が軽減されることにより医師の過労やストレスを減少させることが期待されます。 さらに、夜勤医はその時間帯に集中して業務を行うため、効率的な患者管理や診療が可能になる場合があります。 しかし、夜勤体制への移行には、新たなシフトスケジュールや人員配置が必要であるので、人員確保が難しいことがあるので注意が必要です。
14. まとめ
医師の働き方改革において、当直体制は大きな影響を受ける分野の一つです。医療機関は、労働基準法を遵守し、医師の健康と安全に配慮した当直体制を構築・運用する必要があります。本稿で紹介したポイントを参考に、自院の状況に合わせた適切な対応策を検討してください。





