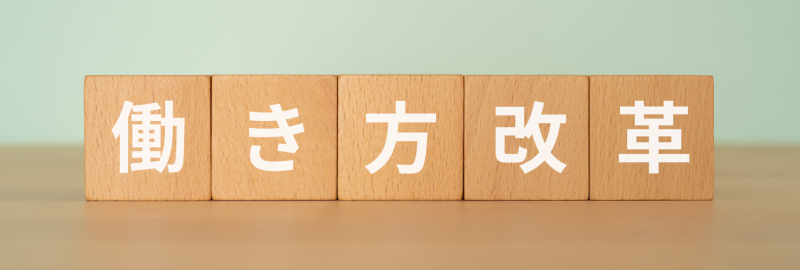
2024年4月から施行された医師の働き方改革は、医療機関にとって労働基準監督署(労基署)の対応も含め、慎重な対応が求められる重要な課題です。本稿では、Q&A形式で、労基署との関わり方、労働基準法遵守、労務管理など、医療機関が留意すべきポイントをまとめます。
1. 労基署との関わり方
1.1 相談窓口の活用
労基署への相談に不安がある場合は、都道府県の医療勤務環境改善支援センターをまず利用することが推奨されます。厚生労働省の資料にも、相談内容は取締り目的で使用されない旨が明記されています。
- Q: 事前に労基署に相談した場合、どう見ても取得できないようであったら労基署から目を付けられますか?それとも親身に相談に乗ってくれますか?
- A: 弊社の調査では、現状「労基署から目をつけられた」といった声は届いておりませんが、もし労基署へのご相談が不安でしたら、まずは、都道府県の医療勤務環境改善支援センターへの相談をお勧めいたします。厚生労働省の案内資料にも「相談時に得た情報は支援のために使用するものであり、取締り目的で使用されません。」と明記されております。
1.2 助成金と労基法違反
労働基準法違反があると、助成金の受給に影響が出る可能性があります。送検されている場合は受給できませんが、申請時に違反が見つかった場合は、改善することで受給できる場合もあります。
- Q: 労働基準法違反になると、ハローワークや労働基準監督署に申請する助成金がストップされた事例があると聞きました。労基違反→ストップはよくあることなのか、個別事象として毎回判断なのかもしわかれば教えていただきたいです
- A: すべての助成金に共通する受給できない事業主のひとつに「支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主」というものがありますが、これは送検されている場合が該当します。
2. 労働基準法遵守
2.1 労働時間の正確な把握
勤務終了時間から帰宅時間までの在院時間について、労働時間、休憩時間、自己研鑽時間などを正確に把握し、記録することが重要です。曖昧な時間帯は労働時間とみなされるリスクがあるため、「自己研鑽」の定義を医師と明確に合意しておく必要があります。
- Q: 勤務終了時間から帰宅時間までの在院時間に何をしていたか(時間外なのか休憩等・自己研鑽なのか)を全て正確に事業所が把握した記録がなければ、在院時間全てについて時間外手当を支払うよう、近隣病院に対し労基署が指示をした事案があると伺いました。こちらは厚生労働省や自治体のルールとしてどこかに記載されているのでしょうか?
- A: ルールとして明示はされておりません。おそらく労基署としては「自己研鑽と明らかにわかるもの以外は、基本的に労働時間とみなしましょう」というメッセージかと思います。労働か自己研鑽か判断がつかないあいまいな時間帯が多く発生する場合、病院側として追加で賃金を支払わなければならないリスクが発生します。「何を自己研鑽とするのか」の定義を医師としっかりとすり合わせておくことが必要です。
2.2 雇用契約の締結と労働条件の明示
医師を採用する際には、労働基準法第15条に基づき、賃金、労働時間などの労働条件を明示する必要があります。雇用契約書を作成し、医師に交付することが望ましいです。
- Q: 地方公営企業である自治体病院において、医師との「雇用契約」が個別に必要でしょうか?
- A: 「雇用契約」が必要になる根拠として、労働基準法第15条第1項の「労働条件の明示」です。使用者が労働者を採用するときは賃金労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければならない、とされており、具体的な明示事項も労働基準法施行規則において定められています。
2.3 労働条件明示時の同意
労働条件を明示する際、医師から「説明を受けて同意します」といった一筆をもらうことが望ましいです。法律上は明示のみが義務ですが、後々のトラブルを防ぐために、署名やメールでの同意返信など、同意の記録を残しておくことが推奨されます。
- Q: 採用オリエンテーションの際に、4月からは「勤務条件の明示」として労基則の必要項目を網羅しておくように修正したいと思います。この際、医師本人から「説明を受けて同意します」みたいな一筆は不要ということでよいでしょうか?
- A: 何かしらの形で同意の一言を残しておくのが望ましいです。法律上は「明示」までが義務ですので一応明示だけでも法律上は問題ありません。ただし、医師からの「聞いていない」等のトラブルを防ぐために、署名を頂いておくのが慣例となっております。
2.4 時間外労働時間の上限
医師の時間外労働時間の上限については、就業規則に記載することが望ましいですが、必須ではありません。36協定で「年960時間、月100時間未満」と締結している場合でも、就業規則に記載する際は、36協定の範囲内であることを明記すると運用しやすくなります。
- Q: 医師の時間外労働時間の上限等について、就業規則への記載は必要でしょうか。
- A: 就業規則の時間外上限については、「職員代表と締結する36協定の範囲内で時間外労働及び休日労働を命じる」などの記載をすることが多いです。上限については必ずしも記載する必要はないかと思いますが、記載があったほうが望ましいです。
2.5 災害時の時間外労働
労働基準法第33条に基づき、災害などやむを得ない理由で時間外・休日労働をさせる場合でも、時間外労働が100時間を超える場合は、医師への面接指導が必要です。
- Q: 現在の就業規則(管理規程)に「特例業務(大規模災害等)に従事する職員に対し、労基法第33条第1項に基づく許可・届出のある場合は、時間外勤務の上限規定は適用しない」旨の記載がありますが、この場合、医師の時間外勤務が月100時間を超過した場合でも、面接指導は必要ないでしょうか?
- A: 労働基準法第33項第1項に基づき、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合、法定の時間を超えて時間外・休日労働をさせることは可能です(事前もしくは事後速やかに労働基準監督署の許可が必要)。ただし、この規定は法定の時間と超えてることが可能になるだけであって、時間外・休日労働をさせたことには変わりないため、この場合に100時間を超過した場合であっても面接指導は必要と考えます。
2.6 労働契約期間
医師の労働契約期間は、原則3年ですが、専門的な知識等を有する労働者として、5年とすることが可能です。
- Q: 労基法14条1項1号によると、医師・歯科医師・薬剤師等は労働契約期間が5年とお聞きしたのですが、あっておりますでしょうか?
- A: 原則は3年ですが、例外として・専門的な知識等を有する労働者、・60歳以上の労働者については、5年とされています。「専門的な知識を有する労働者」として5年の特例が認められているのは以下の基準を満たす労働者です。
3. 労務管理
3.1 宿日直許可の実態調査
労基署が宿日直許可の実態調査を行う場合、過去3か月分の実績を元に調査を行うのが一般的です。
- Q: 宿日直許可を得る際、労基署の実態調査は過去どれだけの期間を元に調査をされますか?
- A: 基本的には、過去3か月分の実績を元に調査を行っています。
3.2 管理監督者の扱い
新規開設クリニックの院長など、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は、労働時間・休日に関する規定が適用されません。ただし、「管理監督者」に該当するかどうかは、役職名ではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断されます。
- Q: 新規開設クリニックの院長となる場合、労基上は管理職扱いとなるため、残業の概念は適用されますでしょうか?
- A: 労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は、労働時間・休日に関する規定が適用されないため、時間外労働の制限や残業代の支払いは発生しません。「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。
3.3 労基署の監査と是正
労基署の監査で問題が発覚した場合、是正勧告や割増賃金の支払い命令などが出される可能性があります。労務管理が適切に行われているか、雇用契約書に勤務条件が明記されているかなどが重要なポイントとなります。
- Q: 働き方改革の適用されてもう少しで1年たつのですが、労基から監査を受け、そのうえで処分や改善指示が出たケースはありますでしょうか。またそのケースの場合、どういった点が問題となったのでしょうか?
- A: 現時点では、大崎市民病院が時間外手当を算出する際に算定基礎賃金に必要な手当を含めていなかったことで残業代の未払いとして、8億円余りを分割支給をした事例や、鹿児島県率病院が労働時間の出退勤時刻が実態との乖離があると判断され割増賃金の支払いを求められたケースがございます。
4. まとめ
医師の働き方改革を成功させるためには、労働基準法を遵守し、適切な労務管理を行うことが不可欠です。労基署との適切な関係を築き、医師の労働環境改善に努めることが、医療機関の持続的な発展につながります。




