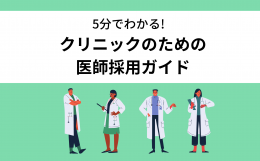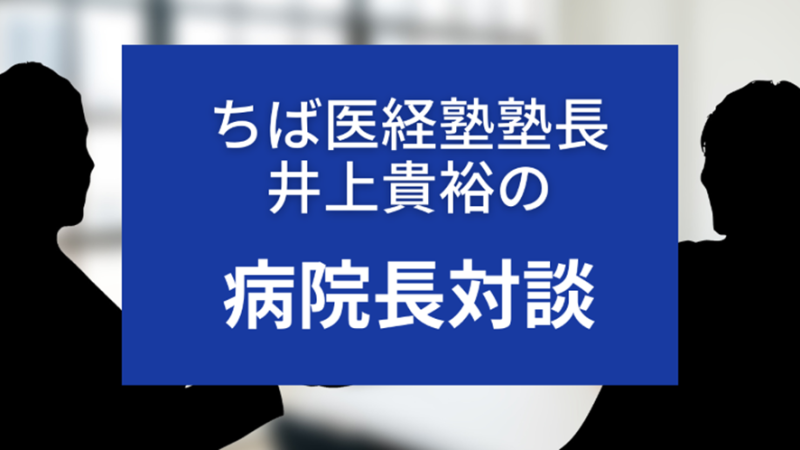
医師の地域偏在をどう解消するか。そして大学病院は今後どうあるべきなのか――ちば医経塾井上貴裕塾長と学校法人東邦大学の炭山嘉伸理事長の対談第3回目・最終回です。創立100周年を迎えた東邦大学の将来展望についてもうかがいました。


初期研修医の集まりにも課題
どうしても地域偏在は起こってしまう
井上貴裕氏(以下、井上):前回は、専攻医は増えるものの博士課程に進む人材が減っている現状について教えていただきました。初期研修医についてはいかがでしょうか。
炭山嘉伸氏(以下、炭山):初期研修医についても、あまり人が集まっていないのが現状です。地方の大学では、初期研修医の集まりも悪いと聞いています。地方では大学に戻っても症例数が少ないため、どうしても医師の地域偏在が起こってしまうのです。
地域偏在を解消するために専攻医にシーリングをかけましたが、これもまた問題です。せっかく人を集めようとしても、シーリングのせいで十分に集めることができないからです。私の大学で言えば、3病院の内科全部で13人しか集めることができません。これではとてもではありませんが、十分に診療をできる人数とは言えません。
高度急性期医療と「最後の砦」を両立するために
医師の給与、教育・研究時間の充実が不可欠
井上:これからの大学病院はどうなっていくかについてもお考えを聞かせてください。
炭山:問題に対する捉え方は、地方と首都圏で異なりますが、大きく私立大学のあり方としては3つのポイントがあります。それは、①高度急性期医療②地域における最後の砦③大学における医師派遣――です。
大学病院として先進医療に取り組みつつ、救急車も含めて地域で行き場がなく困っている患者の最後の砦となる。そして、医師を派遣できる機能を維持することが大学病院の使命です。そのためには大学で働く医師たちがしっかりとした給与を得て、同時に研究や教育に充てる時間を確保できる体制の維持が不可欠です。このことを私はずっと発信し続けていきたいと考えています。
東邦大学創立100周年。建学の精神を尊重し、法人全体が一枚岩に
「大森病院の新築、何としてもやり遂げたい」
井上:東邦大学は今年100周年を迎えました。理事長に就任してからこれまでを振り返り、また今後についてのお考えを聞かせてください。
炭山:理事長に就任以来、建学の精神を大切にした法人運営を心がけてきました。それまでは、同窓会を含めてそれぞれの学部がバラバラで活動しているような面もありました。しかし、資料室を建てたり『額田豊・晉の生涯: 東邦大学のルーツをたどる』(中央公論事業出版)という書籍を出版したり、建学の精神にのっとって法人全体で統一感を持ってもらうように取り組みを進めました。私が長年にわたり理事長として信頼を得ることができたのは、何よりも建学の精神を尊重したことが理由の一つだと考えています。
創立100周年を迎えて、社会の動向では少子高齢化の進展や診療報酬の改定率、消費税増税の有無などさまざまな課題があります。こうした中で、取り組みたいと考えているのは①災害対策の強化(危機管理のあり方)②大森地区再開発プロジェクト③習志野地区長期計画プロジェクト④記念式典と祝賀会――です。
災害対策では、耐震化率を現在の93%から2028年度までに100%に引き上げることを目指します。また、大森地区の再開発では、新外来棟の建設や周産期センターの移転を含む大森病院2号館の補修工事、臨床研究棟跡地にメディカルリサーチセンター建立――を計画しています。
今は建築費用の高騰によって、さまざまな病院が建て替え計画を中断していると聞きます。しかし、私は計画通り大森病院の新築プロジェクトを進めるつもりです。そのために、これまでの任期でしっかりと準備を進めてきました。これは私にとっての最後の大きな仕事になるかもしれませんが、現場でがんばってくれている職員たちへの感謝の気持ちとしても、ぜひとも成し遂げたいと思っています。
井上:大学病院の今後のあり方から、東邦大学の展望までうかがうことができました。ありがとうございました。
(取材・文 医療ライター横井かずえ)