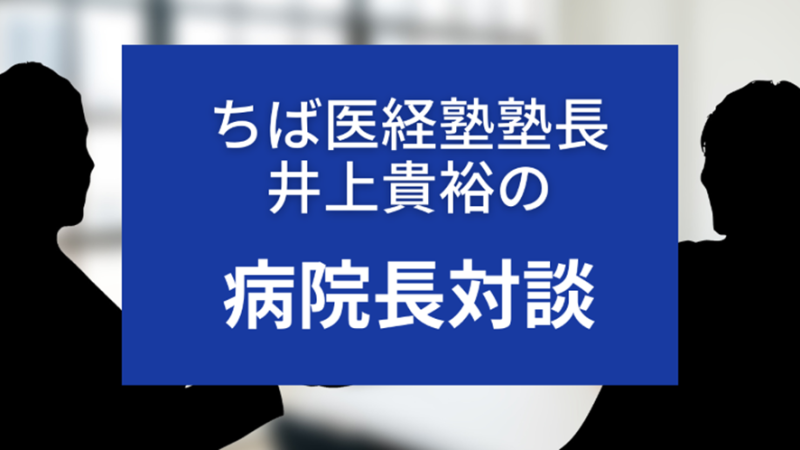
附属病院の経営難や大学院進学率の低下…私立医科大学を巡る課題をどう乗り越えるのか――ちば医経塾井上貴裕塾長と学校法人東邦大学の炭山嘉伸理事長の対談第2回目は、日本私立医科大学協会の会長としての活動についてお話を聞きました。

「人生は何が起こるか分からない」
医大協の第14代目会長に就任、医学教育の将来のために尽力
井上貴裕氏(以下、井上):炭山先生は、一般社団法人日本私立医科大学協会の会長も務めておられます。会長になられた経緯を教えてください。
炭山嘉伸氏(以下、炭山):2024年の3月に前会長の小川彰先生が急逝されて、私が後を引き継ぐ形で会長に就任しました。それまで私は病院担当の副会長として、ロビー活動や省庁を回るときなど、いつも小川先生と一緒に活動してきました。そうした活動の中で小川先生の信頼を得ていたこともあり、理事会から満票で選任され14代目の会長となったのです。
島育ちで海や山の中を走り回っていた自分が、まさか全国の医大協の会長になるなど、夢にも思いませんでした。本当に、人生は何が起こるかわからないものです。今は、医大協会長として、医学教育に関する将来検討など、学校法人の理事長職以外の仕事に忙しくしている毎日です。
私立大系列88病院のうち、黒字はたったの10大学
ほぼすべての病院が赤字に転落の危機を前に「増収減益」の厳しさを訴え
井上:2025年1月22日には、医大協として初めての記者会見を実施しました。
炭山:厳しい経営状況を含めて、私立医科大学の現状を多くの人に知ってもらうために会見を開きました。私立医科大学病院は、「増収減益」の厳しい経営が続いています。医大協に加盟しているのは30大学で、病院としては本院30病院、分院58病院合わせて88病院です。加盟大学の附属病院の収支をみると、2023年度は10大学がプラス、20大学がマイナスの収支で、黒字だったのは10大学しかありませんでした。
さらに、2024年度はほぼすべての病院が赤字に転落する危機にあるとみられています。診療報酬が現在の物価高騰に対応しきれていないことが一因で、2024年度改定は実質マイナス改定だったと私たちは解釈しています。
本学はかろうじて黒字ですが、これは薬学部、理学部、看護学部などを持つ複合大学だからです。病院経営だけで見れば、本院は黒字ですが2つの分院は赤字であり、3つの病院を合わせればトータルでは赤字です。本学の例で言えば、事業収入の構成比は医業収入が75%を占めているため、やはりいかにしてここを改善するかが重要なポイントです。
現状、本院については特定機能病院として、一定の要件を満たす場合にさらにインセンティブがつく方向性が示されています。先日開かれた厚生労働省の「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」でも、そのような方向性で議論がなされました。
一方で、分院に対してはこのようなインセンティブはありません。大学附属病院の多くが赤字である現状を考えると、分院に対しても特定機能病院に準ずるような、何らかの対応が必要だと私たちは考えています。
井上:本院と分院では、どちらの業績が良い大学が多いのですか。大学によってさまざまなのでしょうか。
炭山:大学によってさまざまですが、研究、教育、医療のそれぞれを各病院で独立採算制にしているケースが最も多いと思います。本院は特定機能病院としてのインセンティブもあり黒字の大学が多いのですが、本院だけが黒字になっても病院全体で言えば赤字に転落してしまうのです。
これは大変大きな問題です。なぜなら、私大病院は国立大学病院と同様に高度急性期医療や地域における最後の砦としての役割、医師派遣の機能を持つほか、教育機能も担っています。医療系教員の65.3%となる1万8198人は私大の教員が占めていて、分院の課す役割は大きな割合を占めていますが私大の附属病院の分院が潰れてしまったらパブリックサービスが失われてしまうことになりかねません。
専攻医増も、大学院進学は激減、研究力低下の懸念も
文科省へ「院進のキャリアパス」創設を要請
井上:教育に従事する教員の給与水準の低さや、研究力の低下も危惧されています。
炭山:同じ医師であっても大学病院に勤務する医師の給与は低く、大きな問題となっています。さらに、もう一つ大きな課題となっているのが、博士課程を取得する医師が大幅に減っているということです。専門医制度ができてから、開業するにしても専門医を取得してから開業したいというニーズが高く、専攻医のカリキュラムは人気です。
初期研修は市中病院などを含めてさまざまな場所で行われますが、専攻医は症例数が必要なのでこのタイミングで大学へ戻ってくるのです。その一方で、大学院に進学して博士号を取得する医師は極めて減っています。専攻医は増えているのに、大学院へ進学する人がほとんどいないというのが現状なのです。
その結果として、今や大学院の進学率は韓国の約3分の1、論文数は世界でも13位で、イランよりも下位です。このままでは、日本の研究力が著しく低下してしまうのではないかと大変、危惧しています。
これには今の制度設計も問題だと感じています。大学で働く人間が快く働けるようにするには、働き方改革の中であっても教育・研究に取り組む時間を確保できて、さらにそれに対するインセンティブなどの評価体制もきちんと整っていることが必要です。しかし、今の制度設計はこれらを奪ってしまっているのです。
この問題に関しては、ぜひとも大学院に進学するためのキャリアパスを作ってほしいと文部科学省に要望しています。初期研修後に一度大学院へ入るのでも良いですし、専攻医のカリキュラムに入ると同時に大学院にも進学できるのでも良いのですが、何らかの制度設計は必須です。これは私自身の大きな使命の一つとして、ぜひとも取り組みたい課題となっています。
井上:ありがとうございます。博士課程へ進む医師の減少を含め、私立大学が抱えている課題について教えていただきました。最終回となる次回は、地域偏在の問題や100周年を迎えた東邦大学の今後などについてうかがっています。
(取材・文 医療ライター横井かずえ)










