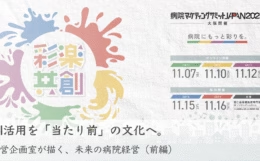2020年度の診療報酬改定に向けて、中央社会保険医療協議会(中医協)の議論が本格化しています。中でも気がかりなのは、従来の7対1入院基本料からほかの点数、特に急性期一般入院料2や3などへの転換を促すためのてこ入れ強化です。中医協の「入院医療等の調査・評価分科会」が2018年度と2019年度に行った2回の調査では、7対1からの転換がほとんど進んでいないことが分かり、支払側からは算定要件を厳格化すべきだという意見も出ています。
<CBニュース記者・兼松昭夫>
支払側・幸野庄司委員「やるべきことがはっきり見えてきた」
入院医療への評価体系は、2018年度の診療報酬改定で大きく変更されました。厚生労働省はこれによる影響を把握した上で、必要に応じた見直しを2020年度の改定で行う方針です。分科会が年度をまたいで2回目の調査を行ったのは、2018年度の改定時に一定の猶予期間が設定された施設も含め、正確な影響を詳しく把握するためです。
9月26日には2019年度分の調査結果の速報が分科会に報告され、改定前に7対1入院基本料を届け出ていた3,513病棟のうち93.5%が、改定後は7対1相当の急性期一般入院料1に移行していたことが分かりました。7対1の転換先として新設された7対1と10対1の中間に相当する急性期一般入院料2と入院料3に切り替えた病棟は、それぞれ3.2%と0.2%しかありません。

図表1 改定前に一般病棟(7 対 1)を届出ていた病棟の令和元年6月1日時点の届出状況 ※2019年9月26日に行われた入院医療等の調査・評価分科会の資料より抜粋

図表2 改定前に一般病棟(7 対 1)を届出ていた病棟の平成30年11月1日時点の届出状況 ※2019年9月26日に行われた入院医療等の調査・評価分科会の資料より抜粋
2018年度の調査も同じような結果で、改定前に7対1を届け出ていた1,801病棟の96.5%が、同年11月の時点で急性期一般入院料1に移行していました。この調査結果は2019年6月12日、中医協の診療報酬基本問題小委員会に速報が報告され、支払側の幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、「次期診療報酬改定で何をやらなければいけないか、2回目の調査で調査結果が大きく変われば別だが、はっきり今の時点で見えてきた」と述べ、急性期一般入院料1の算定要件を厳格化する必要性を示唆していました。
急性期一般入院料2・3への転換が進まない理由
2018年度の診療報酬改定では、従来の一般病棟入院基本料のうち7対1と10対1を急性期一般入院基本料に再編・統合し、急性期一般入院料1~7という7つの点数を新たに設定しました。
ポイントは、急性期一般入院料2と入院料3をつくったことです。7対1相当から10対1相当に転換することで急激な減収になるのを防ぐため、従来の10対1よりも点数が高く設定されました。それによって、急性期一般入院料1から入院料2と入院料3への転換がどれだけ進むのかが注目されていましたが、分科会の松本義幸委員(健康保険組合連合会参与)は9月5日の会合で、「期待した結果は得られなかった」との受け止め方を示しました。
2回目の調査では、急性期一般入院料1を届け出る病棟の8割ほどが今後の意向に関する質問に「現状を維持」と答えました。これを見る限り、急性期一般入院料1の届け出は今後も減りそうにありません。
政府が6月に閣議決定した骨太方針2019では、入院基本料の見直しによる病床再編への効果の検証を求めていて、財務省が今後、2020年度改定での引き締めを求めるのは確実です。

図表3 今後の届出の意向 ※2019年9月26日に行われた入院医療等の調査・評価分科会の資料より抜粋
転換が進まないのはなぜでしょうか。原因の一つとみられるのが、2018年度に行われた「重症度、医療・看護必要度」の評価の見直しです。「重症度、医療・看護必要度」は、入院患者に対して急性期の対応がどれだけ必要かを測るためのツールで、2008年度の改定で「看護必要度」として導入されました。その後に何度も見直され、現在では、モニタリングや処置の実施状況(A項目)、寝返りを打てるかなど患者の状況(B項目)、開頭や開胸手術を一定期間内に実施したかなどの医学的状況(C項目)の3つの観点を組み合わせた評価票で患者の状況を評価しています。

図表4 一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度の見直し」(評価表について) ※2018年3月5日に行われた2018年度診療報酬改定説明会の資料より抜粋
2018年度の改定前まで「急性期の患者」とみなされたのは、
・A項目が3点以上
・C項目が1点以上
の3つの基準のどれかに該当するケースで、そうした患者を全体の「25%以上」受け入れることが7対1入院基本料の算定要件の一つでした。
2018年度の改定で国は、この受け入れ割合を「30%以上」に引き上げる一方、「急性期の患者」に該当する患者の範囲も拡大しました。これまでの3つの基準に加え、B項目のうち、認知症関連の、
の基準に該当する場合も、「急性期の患者」とみなせるようになったのです。
BPSD(認知症の行動・心理症状)を伴うなど、診察や看護の提供頻度が高い認知症がある患者を7対1病棟でもそれなりに受け入れていることが分かったため、新たな基準をつくって評価することが狙いでした。

図表5 7対1 一般病棟における認知症・せん妄の患者 ※2017年11月24日に行われた中央社会保険医療協議会・総会の資料より抜粋
急性期機能の高さを判定するはずなのに
ところが、急性期病棟の患者を評価する物差しとして、この新たな基準がふさわしいのか、疑問視する声が上がっています。この基準をクリアする病棟では、要介護度の高い患者や80歳以上の患者の割合が多い傾向にあることが、分科会の調査で分かったためです。「重症度、医療・看護必要度」は本来、急性期機能の高さを判断するためのツールなのに、これでは高齢者を積極的に受け入れる病院ほど有利になりかねません。
実際、厚労省が10月16日に公表した分析結果によると、この基準にのみ該当する入院患者の割合は、従来の療養病棟入院基本料1で14.6%だったのに対し、7対1入院基本料では4.7%。療養病棟入院基本料1での割合は、18年度改定前の5つの点数で最高でした。

図表6 基準2のみに該当する患者の割合 ※2019年10月16日に行われた入院医療等の調査・評価分科会の資料より抜粋
厚労省の研究班の調べでは、「急性期の患者」を定義する4つの基準のうち、新たな基準のみをクリアしている入院患者は全体の5.9%を占めています。分科会の9月5日の会合で厚労省は、病床規模が小さい病院ほどそうした患者の割合が高い傾向にあることを示す参考データを公表しました。認知症への対応を評価するこの基準がもし廃止されたら、急性期一般入院料1から入院料2や入院料3への転換を迫られる中小病院が出てくるかもしれません。

図表7 看護必要度の基準(旧、2018年度)を満たす患者割合(各基準別) ※2019年9月5日に行われた入院医療等の調査・評価分科会の資料より抜粋
「重症度、医療・看護必要度」の変更は、2018年度の改定でも大きな焦点になりました。基準を1つ追加した上に、受け入れ割合の基準値を「25%以上」に据え置くよう診療側が譲らず、議論が平行線をたどったのです。そのため、最後は中立の公益委員の裁定で「30%以上」への引き上げが決まりました。幸野委員はその際、「最悪の事態は避けられた」と述べる一方、「これで本当に入院医療の機能分化が進むのか、非常に疑問だ」と懸念も表明していました。
幸野委員の懸念は、2回の調査で図らずも裏付けられてしまいました。2020年度の見直しを巡り、今度はどのようなさや当てが繰り広げられるのでしょうか。