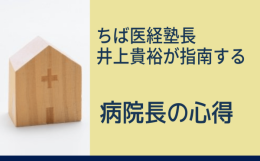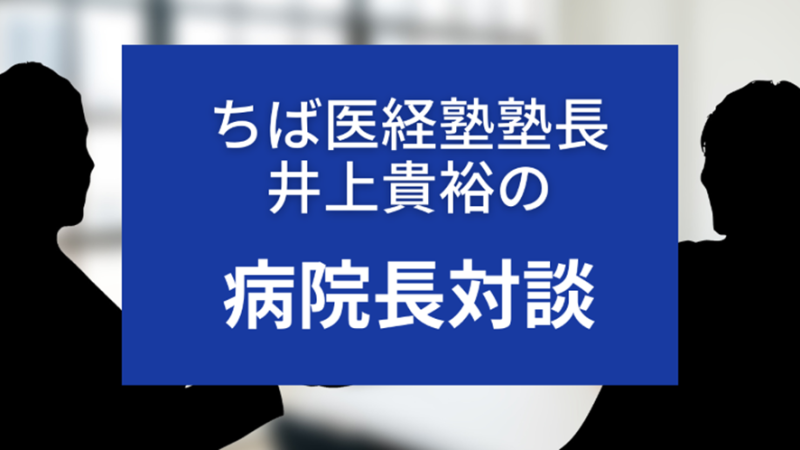
診療報酬のマイナス改定や消費増税などの逆境に負けず、業績を大きく伸ばした方法とは――ちば医経塾井上貴裕塾長と病院経営者の対談シリーズ。今回は、学校法人東邦大学の炭山嘉伸理事長がお相手です。東邦大学の経営改善に取り組み、創業者を除き最長の就任期間となった炭山氏の半生をうかがいました。
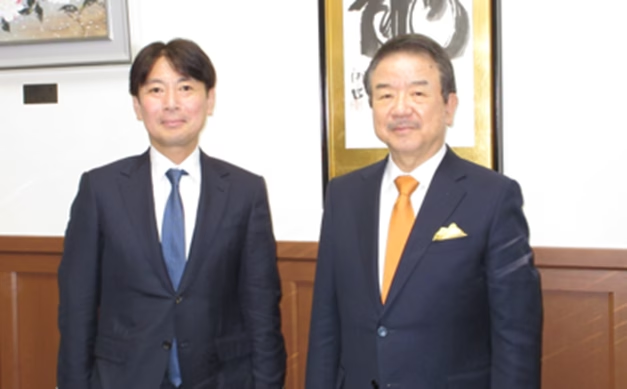
土地を用意して待っていた父を説得し…地元で開業予定が一転。
後輩に慕われ、上司に愛され45歳で教授に就任
井上貴裕氏(以下、井上):はじめに先生のご経歴を教えてください。
炭山嘉伸氏(以下、炭山):私は香川県の小豆島出身です。小豆島は瀬戸内海にある島で、幼少期は海や川で泳いだり山野を駆け回ったりなど、伸び伸びと育ちました。もともとは弁護士を目指していて、上京して一度は法学部に入学しました。しかし、大学3年生のときに虫垂炎になり、小豆島で開業していた義理の兄に虫垂炎の手術をしてもらったのをきっかけに、外科医にあこがれるようになりました。そこから進路を変更し、10か月間死に物狂いで必死に勉強して東邦大学医学部に合格。医師への道を歩み始めたのです。
医師になって入局してからも、実は長く大学に残るつもりはありませんでした。家族からは地元に戻って開業するように言われていて、父は私のために土地まで用意してくれていたからです。
しかし、学生時代にテニスに打ち込んで実績を残したこともあり、部活の後輩が私を慕ってくれて次々に入局してくれました。そのことを恩師が評価してくれて、大学に残るように慰留されたのです。最終的に、恩師が小豆島まで出向いて家族を説得し、大学へ残ることが決まりました。なお、私を慕って入局してくれた後輩たちのうち、今では6人が外科学教室の教授になっています。
大学に残ることが決まった2カ月後には、米国留学が決定し、ハワイ大学、スタンフォード大学、メイヨークリニックに留学しました。そして、当時の外科の教授としては最年少の45歳で教授に就任しました。
東邦大学の名を世に知らしめるため、13の学会・研究会で会長に、病院長の面白さに目覚め、病床稼働率は一気に93%を達成
井上:教授に就任後はどのような活動をされたのですか。
炭山:教授に就任してからは、大学の役職よりもむしろ外に目を向けて、学会活動に明け暮れました。東邦大学の名前を知らしめる方法はなにかと考えたら、やはり学会活動が大切だと思ったからです。そこで日本外科感染症学会や日本感染症医薬品協会の理事長、日本消化器外科学会をはじめとして13の学会や研究会の会長を務めました。
学外の活動に身を投じている中で、第7代の野口鉄也理事長から「将来、君は東邦大学法人の理事長になれ」と言われました。理事長になるためには、病院長を経験する必要があります。そこで急遽、大橋病院の病院長を務めることになったのです。
はじめは渋々引き受けた病院長職でしたが、いざ務めることになったらたちまち病院経営の面白さに目覚めました。もともと弁護士を目指していたこともあり、ビジネスや経済には興味があったからです。
大橋病院長としての3年間はほとんど病院長室から出なかったくらい病院経営に夢中になりました。毎朝7時半くらいからベッドの稼働状況を確認し、当時470床だった同院の稼働率を93%まで引き上げ、一気に経営改善しました。
その実績が評価され、2009年に66歳で学校法人東邦大学の理事長に就任。2期目からは理事会・評議員会で無記名投票による満票で選任され、現在は6期目を迎えました。これは、創業者を除いた本学出身者としては最も長い任期となります。
約1050億円を投じて経営改善。
診療報酬改定・消費増税のなか、実質無借金経営を達成
井上:理事長に就任後は、さまざまな経営改善に取り組まれたと聞いています。
炭山:理事長に就任してからは、来るべき厳しい将来を見据え、早くから安心・安全で魅力ある医療・教育環境を作り上げるために、さまざまな経営改善策に取り組んできました。
具体的には第1~5期の間に合計約1050億円を投資し、計画的に施設・設備の整備を実施しました。さまざまな設備投資はもちろんのこと、高度急性期病院に相応しい医療の提供を目指し、土日の活用や祝日の平日化を含めた効率化にも取り組みました。
そうした取り組みが功を奏し、診療報酬のマイナス改定や消費増税などにもかかわらず、業績は大きく改善して総資産は1435億円になりました。また、現在まで現預金額が借入金額を上回る、実質無借金経営を続けています。
井上:ありがとうございます。小豆島出身で弁護士を目指していた炭山先生が、さまざまな導きによって図らずも東邦大学の理事長職になるまでをうかがいました。次回は日本私立医科大学協会会長の立場からお話をうかがいます。
(取材・文 医療ライター横井かずえ)