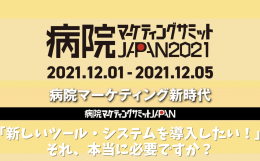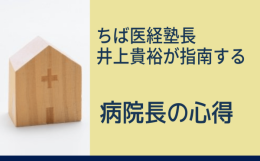本連載について
人口減少や医療費抑制政策により、病院は統廃合の時代を迎えています。生き残りをかけた病院経営において、マーケティングはますます重要なものに。本連載では、病院マーケティングサミットJAPANの中核メンバー陣が、集患・採用・地域連携に活用できるマーケティングや広報の取り組みを取材・報告します。
著者:松岡佳孝/病院マーケティングサミットJAPAN 医療マーケティングディレクター
済生会熊本病院 経営企画部 経営企画室長 兼 広報室長
前回は医療法人松田会松田病院事務部の佐竹直也事務部長に、病院経営に生成AIを活用しようと思ったきっかけや導入までのプロセスについてうかがいました。今回は、佐竹さんオススメの生成AIツールについて具体的にご紹介します。
佐竹事務長オススメ!よく使う生成AIツール
具体的に現在活用しているのは次の5つのツールです。
- ChatGPT:万能型のチャットボット生成AIとして幅広い用途に活用
- Gemini:音声ファイルの要約機能を持ち、議事録作成が大幅に効率化
- Claude:日本語の文章校正が得意なツールで、メール作成や構成案作成に活用
- Perplexity:検索機能に優れ、医療情報の収集に最適
- Felo:入力内容を整理し、マインドマップとして可視化することで、思考を深める助けに
この中で課金をしているのはChatGPTだけだそうで、お金をかけずとも業務効率化に取り組めることを再認識しています。
【POINT】ChatGPTの有料版でできること
ChatGPTの有料版では、より高度な機能が利用でき、特に「マイGPT」というカスタマイズ機能を活用することで、業務の効率化が進みます。たとえば、Googleの口コミに自動で返信するBOTを作成することができます。ネガティブな口コミに対する返信は難しいことが多いですが、マイGPTの生成AIを使用すれば、主観や感情を排除した客観的な返答を作成することができます。
さらに、病院内でよくある課題として、内線電話帳が紙ベースで3~4枚分もあり、必要な番号を探すだけで時間がかかってしまうという問題があります。この問題を解決するために、マイGPTの機能を使って業務用の番号を検索しやすいツールを作成することが可能です。このツールは、ログインすれば無料で作成でき、院内のイントラネットで公開することもできます。これにより、業務が大幅に効率化され、時間の節約にもつながります。
無料の生成AIでできる実務改善4例
①苦手意識を持つ人の多いVBA(Visual Basic for Applications)を活用した効率化
VBAは、Microsoft Officeのアプリケーションを操作するためのプログラミング言語のことです。佐竹さん、以前からVBAには苦手意識があり、使っていなかったといいます。
「たとえば年次業務で領収書を大量に発行しなければならない際、すべてエクセルで一つ一つ作成していました。やっても“差し込み印刷”くらい・・ただ年に1度だと毎回やり方を見返しながらやっとできる、という状態でした。しかしChat GPTがVBAのコードを自動生成し、作業時間を大幅に短縮することができました。」
②ケアマネージャーの議事録作成の効率化
ケアマネージャーは、多くの利用者を担当し、そのサービス担当者会議の議事録を作成する必要があります。たとえば、50名ほどの利用者を担当する場合、それぞれの利用者とキーパーソンとの会議を行い、その内容を記録しなければなりません。この作業は非常に負担が大きく、ケアマネージャーが16時ごろに事務所へ戻った後、2~3時間もの残業を強いられることが一般的でした。その結果、ケアマネージャーという職業の人気が低下する要因の一つとなっていました。
そこで、複数の事業所で新たな方法を導入しました。その方法とは、iPadを使って会議の内容を録音し、その音声ファイルをGoogleドライブにアップロードするというものです。事務所にいるスタッフがその音声をもとにレポートを作成し、ケアマネージャーはそれを確認してOKを出すだけで済みます。
この仕組みを導入したことで、実際にケアマネージャーの残業時間が大幅に削減されました。この取り組みを資格手当として評価できないか、という声も上がっています。しかし、100名ほどいるケアマネージャーの中で、この仕組みを活用しているのは、現時点ではまだ2~3名にとどまっています。今後、さらなる普及が求められます。
③発表スライドチェック
発表用のスライド作成時に、ChatGPTやClaudeを活用してスライドチェックを行うことができます。たとえば、結語が弱い部分や表現が不適切な箇所を指摘してもらうことができ、これにより完成度の高いスライドを作成することができます。
実際にスライドをチェックにかけると、「もっと強い結論にした方が良い」といったフィードバックがもらえることもあります。このような指摘を受けて修正を加えることで、スライドが一層引き締まり、発表時の印象も大きく向上します。スライドチェックを通じて改善点を見つけられるため、ChatGPTを活用する価値を実感することがよくあります。
④自分自身の思考の整理
佐竹さんは、自身の思考を整理するためにFeloというツールを活用しています。最初に自分の考えていることをアウトプットします。iPhoneのメモ機能を使い、マイクマークを押して話すだけで、自動的に文字に変換されます。しかし、そのままでは「てにをは」も曖昧で、文章が乱れてしまうことが多くあります。
そこで、佐竹さんはFeloにその文字起こしした文章をコピペします。すると、Feloが内容を整理し、わかりやすくまとめてくれるだけでなく、マインドマップとして視覚的に整理してくれます。この過程で、自分の考えが客観的にフィードバックされ、より深く、質の高い思考へと発展していくと感じています。
また、佐竹さんは調べた内容をパワーポイントやマインドマップとして整理し、仕事や学びに活かしています。Feloを活用することで、思考を可視化しながら、より洗練されたアイデアを生み出せるようになりました。
生成AI導入の課題と病院内の反応
生成AIの導入にあたって、佐竹さんは最初、周囲の理解を得ることに苦労しました。はじめは生成AIの可能性に興味を示す人は少なく、導入に向けた議論を進めることが容易ではなかったようです。
しかし、佐竹さんの実績が次第に認知されるようになり、少しずつ導入を試みる職員が増えてきました。「医療は業界特性上、変容を受け入れにくい特徴があると思っています。しかし、一度便利さを体感すると、その有用性を実感してもらえます。そうすることで、徐々に広がっていくと感じています」と佐竹さんは話します。
実際、佐竹さんは少数の熱心なメンバーとともに試行錯誤を重ね、生成AIの活用方法を模索しました。導入の障害となっていた「現状維持バイアス」に対して、具体的な成功事例を示しながら丁寧に説明を重ねることで、少しずつ理解を得ることができました。その結果、現在では病院内でも生成AIの利便性が認識され、活用を検討する職員が増えつつあります。先述した事例もまだまだ道半ばとのことですが、少しずつ広がることに期待が寄せられます。
しかし、生成AIを導入する際に必ず議論に上がるのが「セキュリティや個人情報の漏洩」という懸念です。この問題を挙げて、「生成AIは使用できない」とする意見も多くありますが、私はこの論点は今後の社会の流れを考えるとナンセンスだと思います。これからの就業人口減少やAIの進化を考えると、今のうちに業務を変えていかなければ、対応できなくなることは明らかです。セキュリティ対策をしっかりと施したうえで、新しい技術を積極的に活用し業務効率を上げていくことが、社会全体の生産性向上にも繋がります。
生成AIが病院経営に与える可能性:未来への展望
佐竹さんは、生成AIが病院経営に与える可能性に大きな期待を寄せています。
「将来的には、標準電子カルテと生成AIを組み合わせることで、さらに効率的な業務運営が実現できると思います。また、個人情報の取り扱いに関する課題をクリアしつつ、AIを活用することで業界全体が進化していくと信じています。」
さらに、佐竹さんは「同じマインドを持つ職員を増やしていくことが重要です。生成AIの活用は、医療・介護業界が直面する課題を乗り越えるための一つの手段です。患者さんとの対面業務に注力できるよう、間接業務はAIに任せる仕組みを作るべきだと思います」と述べています。
まとめとメッセージ
生成AIを活用することで、想定以上の効果が得られました。「AIを活用することで、職員間のコミュニケーションがスムーズになりました。AIが事務作業を引き受けることで、対面での業務に集中できる時間が増え、患者さんへのサービス向上にもつながっています」と佐竹さんは話します。
佐竹さんの挑戦は、病院経営に新たな可能性をもたらしています。生成AIを活用することで、業務効率化だけでなく、働きやすい環境づくりや患者サービスの向上にも寄与しているのです。
最後に、佐竹さんから今後生成AIの導入をすすめる方へのメッセージをご紹介します。
「まずは簡単な壁打ち作業から始めてみてください。使ってみることで、生成AIの可能性に気づくはずです。事務部長として、持続可能な病院経営を実現するために挑戦を続けていきます。これからの医療業界には、AIを使いこなせる人材が必要です。ぜひ一歩踏み出してみてください。」
佐竹さんの取り組みは、バックオフィス業務における生成AIの活用をさらに広げるきっかけとなるでしょう。また事務方のためだけでなく、「医療者がより患者さんに向き合うため」に模索されている取り組みです。その歩みは、未来の医療経営における新たなスタンダードを築いていくに違いありません。