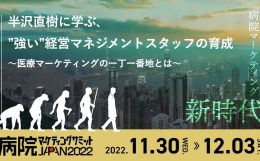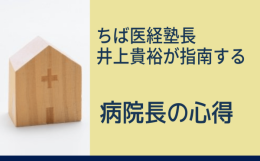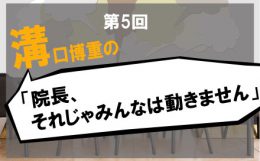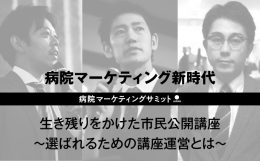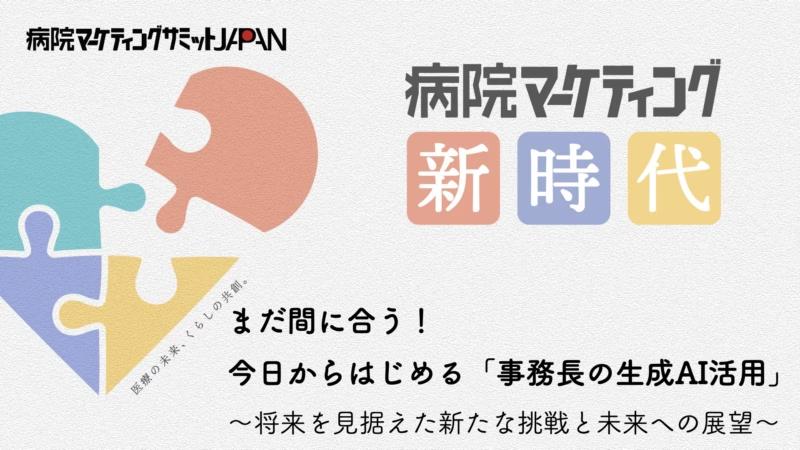
本連載について
人口減少や医療費抑制政策により、病院は統廃合の時代を迎えています。生き残りをかけた病院経営において、マーケティングはますます重要なものに。本連載では、病院マーケティングサミットJAPANの中核メンバー陣が、集患・採用・地域連携に活用できるマーケティングや広報の取り組みを取材・報告します。
著者:松岡佳孝/病院マーケティングサミットJAPAN 医療マーケティングディレクター
済生会熊本病院 経営企画部 広報室長 兼 医療支援部 医事企画室長
生成AIを活用した病院業務の改善
本記事では、実務で生成AIを積極的に活用されている佐竹直也さん(医療法人松田会 松田病院 事務部 部長)の取り組みに焦点を当てます。佐竹さんは、12年前に診療放射線技師としての専門的なキャリアから事務職に転じ、病院の組織運営や経営戦略に深く関与するようになりました。現在は法人全体の経営管理を担う事務部の部長として活躍されています。病院機能評価の受審や組織変革などを通じ、医療経営の面白さを実感する一方で、医療業界特有の低利益構造の理解と、その環境の中での、効率的な運営や処遇改善を模索されています。
そんな佐竹さんが注目するのが、生成AIを活用した業務効率化と組織改善です。佐竹さんの取り組みに注目した理由は大きく2つ挙げられます。
- AIを活用した「目の前の業務効率化」を重視し実践されている点
- 中長期的な視点で「医療業界の課題解決」に挑んでいる点
医療業界は人手不足や運営コストの高騰といった深刻な課題を抱えていますが、佐竹さんの取り組みは、誰でも、明日からでも取り組むことのできる模範事例として課題解決の一助になるのではと考え、インタビューさせていただきました。
本記事では、今後を見据えて「いま」の課題を解決するリアルな挑戦とその未来への展望を紐解いていきます。生成AIを活用した業務効率化に挑戦する背景や意義は何か?活用を進めるに至った理由とは?その具体的な成果に迫ります。

「生成AIは実務に使える、いや使っていかなければならない」と確信
生成AIに興味を持ったきっかけ
佐竹さんが生成AIに興味を持ち始めたのは、今から約2年前のことです。当時、ChatGPTの初期版が話題になり、佐竹さんは医療経営における新たな可能性を感じました。きっかけとなったのは、医療分野の勉強会やコミュニティでの学びでした。特に、長 英一郎氏(東日本税理士法人代表)の主催するサロンでの学びが契機となり、AIが業務効率化に与えるインパクトに驚きを覚えたと語ります。
「最初は半信半疑でしたが、無料で試せるという点もあって、とにかく触ってみました。部下に聞くような些細な相談や、Google検索のようにAIを利用していました。しかし、その後拡張機能が追加されて本当に驚き、「これは実務に使える、いや使っていかなければならないと確信しました」と、佐竹さんは当時を振り返ります。
驚くべき速さで進化する生成AI
たとえば、ChatGPTがリリースされた当初、ユーザーができることはテキストベースでの対話や質問応答など、比較的シンプルな使い方でした。しかし、技術が進化する中でAIにできることも広がり、『PDFを読み込み要約する』などの機能が追加されました。ユーザーは単にPDFをアップロードし、どの部分を要約してほしいのかを指示するだけで難しい資料が要約されるのです。専門的な知識や設定は一切不要。たとえばChat GPTのプロンプト(指示を入力する欄:図1)に「このPDFを要約して」とシンプルに入力するだけで、AIがその内容を理解し、適切に要約を生成してくれるわけです。
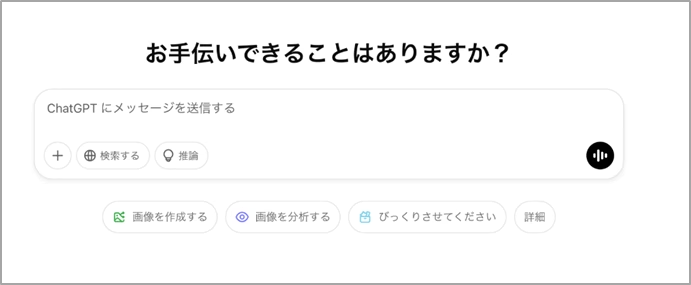
「特に医療業界は霞が関で作成された難解で膨大な資料が多く、その要約が一瞬で叶うだけで感動でした」と佐竹さんは話します。この機能にインパクトを受け、本格的に生成AIを日常的に取り入れはじめたそうです。
生成AI導入までのプロセス
いざ実践!〜職員の残業を減らしたい!〜
ChatGPTにより生成AIへの抵抗感がなくなり、業務改善の手応えを得た佐竹さん。次の実践ステップとして、用途に応じたツールの使い分けを開始しました。その後、Geminiを使って会議の録音を要約し、それを議事録として活用。これまでは半日かけていた文字起こしが、Geminiを使うことで、録音した音声データをAIが自動で要約し、短時間で簡潔な議事録を作成できるようになりました。担当者にとっても、議事録作成業務が劇的に楽になったようです。
「残業が5分でも10分でも短くなれば、スタッフは幸せじゃないですか。医療業界は他業界と比較し給与水準が良いとは言えない業界です。業務を圧縮して残業代を削減し、本給等の待遇改善を本気で考えないといけないと思っています。」
佐竹さんは続けます。
「新卒入職者が23歳とすると、その方々が生まれたのは2002年です。同年の出生数は115万6000人1)でした。一方で2024年の出生数は68万5000人2)です。いま生まれた子どもたちが就職をする2040年代、単純計算しても就職希望者の母数は6割くらいになってしまいます。」
こういった背景も、佐竹さんが本気で業務の効率化に取り組む理由の一つとなっています。経営者の視座でチャレンジされている佐竹さんの信念を、筆者は感銘を受けました。
次回は佐竹さんがおすすめする無料生成AIツールと活用事例をご紹介します。
1)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei02/index.html#:~:text=%E5%87%BA%E7%94%9F%E7%8E%87%EF%BC%88%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%8D%83%E5%AF%BE%EF%BC%89%E3%81%AF、%E5%B9%B4%E3%81%AE9.3%E3%82%92%E4%B8%8B%E5%9B%9E%E3%82%8B%E3%80%82
2) https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=109244