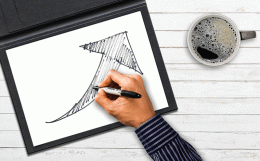看護教員小栗妙子
2017年7月11日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行
この4月で看護教員として11年目の春を迎えた。私が教員になってから関わった学生は550名を越えた。現在は、看護専門学校で終末期看護を教えている。終末期患者と関わることで学生が看護職の「アイデンティティ」を確立していく基礎づくりとなることを目指して取り組んでいる。私は、今年を「今までの学生の指導方法を振り返る時期」だと考えて、看護教育学を深められる大学院に進学しようと決めた。これから「研究」を進める決意をここで示すとともに、その背景となる私自身の看護師、看護教員としてのあゆみを振り返ってみたいと思う。
私の「教員」に対する最初のイメージはネガティブなものだった。それは、小学生の頃に教師の体罰に耐えられず不登校になったからだった。親に迷惑をかけてはいけないと思い、事実を両親に話せずに、仮病を使って何度も学校を休んだ。無気力、拒食に苛まれる辛い日々が続き、次第に周囲の目を気にするようになり、大人の男性に恐怖と不信感を抱くようになった。
そんな私を救い上げてくれたのが小学校高学年で出会ったA先生だった。当時新任だったA先生は、学級全員の主体性を大切にして、どの学生に対しても平等に対応する先生であった。何事にも自信のなかった私の個性を見抜き、どんなことでも挑戦していいということを教えてくれたA先生との出会いは、私の「教員」に対するネガティブなイメージを変え、その後の私の人生を大きく変えるものであった。
その後、私は看護師としての道を選択した。そのきっかけは、当時の家庭の経済状況を見て「手に職をつけて一生働くことができる職業」をしたいと考えたからだ。さらに、看護師を目指すにしても、最低限の学費で済むように、国立病院附属の看護学校に入学して3年間を過ごした。3年間の寮生活は良い仲間に恵まれ、最高の学生時代を過ごすことができた。
私の十数年にわたる看護師経験は、すべて脳外科病棟でのものであった。そこでは、病態が悪化して死に至る可能性の高い患者とその家族、急性期を脱して社会復帰を目指す回復期の患者、慢性期へ移行してリハビリテーションを重ねながら障害とともに人生を歩む患者など、様々な方々と関わってきた。看護師としての最後の数年間は、療養型病棟で主に遷延性脳機能障害などで入院が長期にわたる患者に関わり、あらゆる病期に応じた看護に携わった。
この間に出会った方々から教わったこと、それは「どんな状況にあろうと今を生きる命の尊さ」であった。人の無限の可能性を信じて戦い続ける患者から、「共に病と闘い生きること」を教えてもらったと感じている。また、植物状態の患者の家族が、もしかすると寝たきりのままで、自分たちの声は本人に届いていないかもしれないと思いながら本人に接する姿を見て、「人生って何だろう」と無力感に苛まれたこともあった。今ではこういった経験が私の大きな財産となっている。
その後、知人から看護学校の教員にならないかと誘いをもらった。当時、開学して1年ほどのその学校へ、私は興味本位で見学に行った。その校舎でたまたま学生からあいさつをされたのだが、あまりの緊張で私はうまく返事ができなかった。学生に関わることが怖くも感じた。そして誰もいない教室に入って教壇に立ってみたが、それだけでものすごく怖かった。人前で話すことが苦手な私はますます「教員は無理だ」と思いながら帰路についた。そこでふと思い返したのは、小学生時代の悩み・苦しみを救ってくれた「教員の関わり」だった。当時の職場で新人教育担当として新人看護師と、臨地実習指導者として看護学生と関わることが多くなっていたこともあり、その後少しずつ看護教育に興味が沸き始めた。
日ごろから病棟でじっくり患者と関わる時間をとれないもどかしさを感じていた私は、看護教員になった自分を想像しては、「1人の患者さんのことを学生とじっくり考えられる職業だとしたら魅力的かもしれない」「やってみてだめならすぐに辞めよう」と様々な考えが頭の中をめぐっていた。そしてようやく教員になることを自らの意思で決めた。
その後、看護教員養成課程へ進み、「看護教育漬け」の充実した1年を過ごした。それを終えてから看護学校で担当した領域は成人看護学の中で「がん看護」を中心とした終末期看護であった。がんに伴う慢性期から終末期における看護を学生に教授していくことに大きな不安を抱いた。私自身が今までにほとんど携わったことのない領域だったからである。そこで終末期看護を一から学び直すことにした。終末期領域が、学生の死生観を培うだけでなく、人生における看護観を左右する大切な領域であることにあらためて気づかされた。学び直しから終末期看護の奥深さを実感して、終末期看護を教える立場である自分自身がもっと死生観を養うことが必要なのではないかと考えた。そこで通信制大学へ進み、心理学を中心に生命倫理や死生学について学びを深めた。
教員になりたての私は、看護師になるための知識を学生に与えなくてはならない、経験のないことは勉強してでも自分が教えていかなければならないと、「教える」ことだけが教育であると思っていた。遅刻をする学生、期限までに課題を提出できない学生に、「なぜ遅れてきたの?」「なぜ時間を守れないの?」と、「なぜなぜ攻撃」を仕かけていた。しかし、今はそれが少し違ったものになってきた。「本当はどうしようと思っていたの?」「本当はどうすればよかったと思う?」というように、相手の気持ちを引き出す言葉を選ぶようになった。
看護学校で関わっている学生の年齢層は幅広い。高校卒業したての10代から40代後半までの成人期にあたる学生と関わってきて、成人教育の視点を意識するようになった。「共に学ぶ」「共に支え合う」「相手を尊重する」という相互関係のもとに主体的に学ぶ大切さを私は実感している。そこで次に、この実感を検証すること、つまり今までの学生との関わり方・指導方法がこれでよかったのかを振り返ることが次のステップだと考えた。
私の念願がかない、看護教育学を深めるために星槎大学大学院に今年から進学した。看護専門学校の教員をしながら大学院に行くということは並大抵なことではない。それは自分が一番知っている。それでも進学しようと決めたのは上司の後押しのおかげである。
そこで私が一番研究したい内容は何か、実は入学が決まってからも悩んでいる。しかし、終末期看護を深めたいことだけは私の頭の中では決めている。自宅で誰かが具合が悪くなると慌てて「お医者さん」を迎えに行き往診してもらう、そし訪れる死を受け入れていく。時代劇や戦前~戦後を描いたドラマで頻繁に描かれている光景である。その後、高度経済成長・ベビーブームを経て、医療の進歩とともに最新の医療が受けられる総合病院が各地に設置され、大病院を受診する敷居が低くなった。治療の延長線上にあるのは「畳の上で死ぬこと」ではなく、「病院で死ぬこと」になった。今では病院で死を迎えるケースが76.2%を占め、自宅でのケースはわずか12.5%と言われている。人の死が当たり前だった時代から、現代では、人の死は病院で迎えるもの、人の死は他人任せで、日頃から人が死ぬことを考えることが少なくなっているといえよう。では、そのような中で「生と死」と向き合っている患者と関わることとはどのようなことを指すのか。
学生はもちろんのこと、教える側の教員も「死」を経験したことはない。終末期看護を学ぶ学生は、確実に死に向かっている患者からの言葉の重みを感じながら、生死の苦しみと立ち向かう患者を目の前にして逃げたくなる感情を持ち、何かできることはないかと患者に声をかけるが苦しみを取り除くことできなくて悩む。その患者を受け持つからこそ出てくる学生の葛藤をそばで見つめながら、学生にそこで何を伝えるべきか、看護職を目指す学生に求められる学びは何かと私自身の悩みも尽きない。
看護教員の使命は、看護師としての知識や技能を見につけさせるだけではなく、その基礎となる「人の命を支える人間性の育成」にあると私は考える。そして終末期看護を教える教員として大切なことは、終末期患者と関わることで学生が自身の看護観を見つめていけるようにサポートすることだといえる。さらに看護職のアイデンティティを確立していくきっかけづくりになってほしいと考える。どんなに素晴らしい技術が提供できて、どんなに頭が良くて知識のある看護師だとしても、真心こもった手のぬくもり、温かいまなざしそして相手を尊重する態度がなくては看護師とはいえない。
10代から40代の学生が一同に会して「生と死」を見つめ学びを共有することは、将来看護職に就いたときの死生観の原点となる。臨地実習で実際に受け持った患者から得られる学びの深さは座学とは比べ物にならない。そこで受けた実習指導者からの指導のみならず、実習中の学生同士の対話も、終末期看護を学び職業意識を培っていくために大切なことであろう。
ここまで書いてきて、患者の死生観に触れた学生がどのように自身の看護観を養っていくのかを明らかにしたいと考えている。終末期看護の臨地実習において、学生が教員や実習指導者からの助言・指導がどのように影響して、看護職業意識につながっているのかを明らかにしたい。そうすることで、終末期看護の教授方法をはじめ、教員と臨地実習指導者の指導方法を改善していきたいと考えている。
私が幼い頃に心に受けた傷は今でも残っている。それでも今はその辛い気持ちを学生に話してみたいと思えるまでに変化してきた。自分に自信が持てず、人前で話すことが極端に苦手だったことが今では私の強みに変わってきた。人にはそれぞれ弱点があるため、悩みや弱さを克服するために努力を重ねていく意味がある。努力したことは自分の力に変えることができる。人前で話すことが苦手だった私は、教員を始めた当初は、講義前に何回も授業案を片手に練習をして講義に臨んだ。
こうして苦労したこと、悩んだ経験が相手の気持ちに寄り添えるきっかけになっていると感じる。今まで関わった学生たちにどれほどのことが伝えられたかは目には見えていない。しかし、看護師を目指して門を叩いてくれた学生達に「何にも代え難い命の尊さ」を考えられる学びの機会を提供したいと強く思っている。そのために教員である私自身が大学院で学びを深めたいと考えている。それを応援してくれる家族、そして後押ししてくれる上司に感謝してこれからも取り組んでいきたい。
略歴
新潟県生まれ。国立病院機構附属看護学校卒業後、脳外科病棟で12年勤務。その後看護専門学校教員。平成26年から同看護学科教務主任として学生指導に従事。
(MRIC by 医療ガバナンス学会より転載)