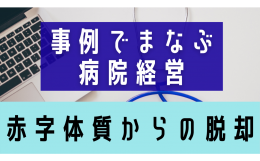- 280床の地域医療支援病院
- 都市部
- 職員数:480名
- 軽〜中等症の新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている(20床)
目次
ケース編
第5波が過ぎ去ったあとも、患者数は戻らず…
都市部にあるA病院は、地域医療の中核を担う地域医療支援病院で、最大20床の軽〜中等度の新型コロナウイルス感染症患者の入院診療を行っている。第5波でも病院をあげてコロナ診療に注力してきたが、最近は落ち着きを取り戻しつつあった。
10月の経営会議の会話
事務長:
感染者数の減少に伴い、発熱外来の売り上げが落ちています。通常の外来患者数は回復してきましたが、コロナ前には到底及びません。
院長:
コロナ患者の入院診療にこれだけの労力を費やしてきたんだ。職員も頑張ってくれたし、十分に地域に貢献しているだろう。
事務長:
それはもちろんでございます。
しかし、地域医療支援病院としての立ち位置を考慮すると、感染状況により外来患者数が左右されているようでは心もとないです。これまでは発熱外来が減収分を補っていたようなものです。
院長:
………。
事務長:
このままコロナ禍が落ち着けば、外来収入は減少するでしょう。外来患者数の減少は新規入院患者数、ひいては病床稼働率に直結するため、経営全体への影響が懸念されます。
対策を考えるためにも、まずは地域連携室に周辺医療機関の動向を調べてもらいましょう。
感染状況によって大きく変動する患者数や、引きつづき警戒・対策を行わなければならない職員の疲弊……。
事務長はwithコロナ時代の病院経営のあり方、そして現状への打開策が見えず、不安を拭いきれなかった。
- コロナ禍がもたらした患者の受療行動の変化とは?
- 訪問によって構築してきた「顔の見える関係づくり」が制限されるコロナ禍で、地域連携の形はどう変化しているのか?
解説編
引き続き、コロナの流行状況に左右される医療機関の経営
怒涛の第5波が過ぎ去り、コロナ診療の現場では落ち着きを取り戻しつつあります。一方で、第6波への備えや新たな変異株への警戒、コロナワクチン3回目接種の準備など、次なる課題への対応に追われている医療機関も多いのではないでしょうか。
加えて、外来患者数はコロナの流行状況に応じて大きく変動します。集患が不安定になることで、病院経営の見通しを立てづらい状況はしばらく続くでしょう。また、2020年のようなコロナ関連の補助金も期待できず、経営者にとっては多くの不安がよぎるところです。
ニッセイ基礎研究所によると、2020年度の概算医療費は42.2兆円で、前年度比にしてマイナス1.4兆円(‐3.2%)。1954年以降、減少額・減少率ともに過去最大の下げ幅となっています。同調査によると、原因は【1】患者の受診控え、【2】病気そのものの減少――と考察されています。
この2つは臨床現場でも話題に上がっているのではないでしょうか。医療機関に足を運ぶことが感染リスクを招くとして受診控えの傾向が強まり、逆に病状の悪化を招くケースも全国的に散見されます。また、感染対策のリテラシー向上によって感染症患者自体が減少し、筆者の勤める医療機関では2020年のインフルエンザの陽性患者は皆無でした。「インフルエンザ薬が売れなかった」「小児科や耳鼻科では閑古鳥が鳴いている」という話も耳にします。
さらに現場では、今秋の緊急事態宣言が明けてから、高齢者の大腿骨頚部骨折が増えている印象があります。近隣の回復期リハビリテーション病院からも同様の声が多数挙がっているため、Stay Homeによる廃用性症候群の増加に、活動の再開が相まった結果と想像できます。
コロナ禍による受療行動の変化と、地域連携への影響とは
このように、コロナの流行は日常生活・受療行動を変化させ、患者数を左右する一因になっています。withコロナの中で、医療機関は新たな経営課題を突きつけられていると言えるでしょう。
A病院のような紹介患者あっての地域医療支援病院にとって、国民の受療行動の変化に伴う紹介患者の減少は、経営の脅威と言っても過言ではありません。地域の診療所の外来患者数減少によってA病院が大きな影響を受けることは必然です。
また、救急医療においてコロナ患者対応が増えるほど、集中治療室や感染対応の可能な病棟はコロナ患者専用と化します。他病棟からの応援人員はもちろん、手術数・外来など、コロナ以外の救急診療の提供量を制限せざるを得ません。
同時に、予定手術の延期や患者の自宅から遠い医療機関への転院、それによるかかりつけ患者の転医など、一般診療の制限は患者の不利益に直結するケースも多々あります。このことが、医療経営に様々な歪みを誘発しています。
さらにコロナ禍によって、地域連携の形・手法も変化せざるを得ません。
たとえば、vol.11で解説したように、これまでは「顔の見える関係」が重視され、特に病院の前方連携では地域の診療所等への挨拶回りが日常的に行われていました。しかし、コロナ禍で訪問活動が敬遠され、対面コミュニケーションの頻度よりも、これまでいかに信頼関係を構築してきたかが、地域連携の生命線となっています。
これからの地域連携には、ICT(情報通信機器)や新たなツールが不可欠に
従来の地域連携は「顔の見える関係」がスローガンのように言われ、Face to Faceが重要と考えられてきました。しかし、コロナ禍に伴い、現在はオンラインでの連携へと変容しています。
Zoomなどのテレビ会議システムが浸透したことで、オンラインでの営業活動への心理的抵抗が軽くなり、むしろ安全で効率的な方法として好意的に認知されていったのです。特にこれまで医療ソーシャルワーカーが電話のやり取りで実施していた転院相談は、「転院をお願いしたい側」と「転院を受け入れたい側」をつなぐマッチングサイトのようなシステムも浸透し始めました。
筆者は医療ソーシャルワークを職人技のように教育してもらえる、恵まれた環境で新人時代を過ごしてきたこともあり、こうしたシステムに当初は抵抗感を覚えました。
転院は、患者やその家族にとってその必要性がある場合に行われるべきです。たとえば “専門的なリハビリを必要とする脳血管疾患の患者が回復期リハビリテーション病棟のある病院に転院する”といったケースですね。
しかし臨床現場では、何のアセスメントもせずに、患者の回転率を高めるために病院を追い出すような転院相談が、一部存在するのも残念ながら事実です。
電話での転院相談は、受け入れ側の医療ソーシャルワーカーが家族の意向やリハビリの改善見込みなど、様々な情報収集を行います。相談元の担当者もしっかりとした状況把握・アセスメントを求められるため、少なからず制御機能が働きます。
一方で、システム上の転院相談はただの“作業”となり、患者の希望・選択が軽視される恐れもあります。これでは、「顔の見えない連携」に逆戻りしかねません。
このため、システムを活用する際は、利用する医療従事者が職業倫理をきちんと身につけていること、マネージャーが適切に管理できることが前提になるでしょう。
一方で、医療ソーシャルワーカーが専門性を発揮した上で、あくまでも手段としてシステムを活用するならば、業務効率・生産性向上が期待できることは言うまでもありません。実際に導入している医療機関の管理者の話では、業務効率の向上により、人員削減も検討していると聞きます。
コロナ対応のみならず、働き方改革や労働世代人口の減少など、現代の労働環境が抱える課題を解決する手段として、新たなツールの出現・広がりは必然です。 固定観念に縛られず、柔軟にこうしたツールを正しく活用することが求められる時代となっているのでしょう。
面会の可否が集患・地域連携にも影響?
また、患者が病院に求める対応も変化しています。コロナの院内クラスターの原因として、患者の転入院の際の持ち込みや、無症状従業員の院内への持ち込みが問題視されました。多くの医療機関では外部からの出入りに厳しい制限を設け、インフルエンザ流行時よりもさらに厳戒な面会制限が全国で実施されています。この結果、患者家族が入院中の患者に会えない、面会制限ゆえに最期に立ち会えない、コロナ陽性患者においては遺骨となって再会といった状況が一般化されてきました。
当初は「しっかりと面会制限をしている病院は安心」という考え方が広がったものの、withコロナ生活が長引く中、患者家族のニーズは「安全対策を施した上で、面会もさせてもらえる病院に入院・転院したい」に変化しつつあります。
感染管理の方法が確立されると同時に、医療機関側も「患者が家族となんとか面会できるようにしたい」と安全な面会方法を模索する施設が増えました。いまや、面会できることは病院の売りであり、患者に選ばれる一要素にもなっています。完全に面会を許可することは難しくても、地域の感染状況をふまえ、フレキシブルに対応できるような体制づくりが求められているのです。
特に地域連携の担当者は、日常的に周辺医療機関の情報収集・交換をされていると思います。たとえば近隣医療機関で面会制限緩和の情報があれば、自院の感染管理委員会に知らせ、自院でも制限緩和を検討してもらうといった働きかけも可能でしょう。
さらには、近隣医療機関の面会制限緩和の情報をきっかけに、タイミング良く訪問活動を再開するのも一つの手でしょう。一方で、面会制限が強化されれば即座に訪問を自粛し、テレビ会議などの方法に切り替えれば、スマートな渉外担当者として認知してもらえるかもしれません。
このように、新しい生活様式は医療機関運営に大きな影響を与えています。一見こうした変化への対応はハードルが高く、悲観的になってしまうかもしれません。しかし視点を変えれば、新たなアイディアの創出やスピーディーな対応によって、競争優位性を高めるチャンスと捉えることもできるのではないでしょうか。
参考
コロナ禍での医療費減少-新型コロナの感染拡大は、受療行動にどのように影響したか? ──保険研究部 主席研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 篠原 拓也
 社会医療法人社団光仁会 第一病院(東京都葛飾区、一般病床101床(うち、地域包括ケア病床12床)・医療療養病床35床)にて医療福祉連携室室長と経営企画室を兼務。医療ソーシャルワーカー(MSW)として亀田総合病院で経験を積んだ後、医療課題は社会経済、経営、マーケティングの視点からも解決していく重要性を実感し、経営学修士(MBA)を取得。その他、医療経営士1級、介護福祉経営士1級などを取得し、講師業などにも取り組む。(過去のインタビュー記事)
社会医療法人社団光仁会 第一病院(東京都葛飾区、一般病床101床(うち、地域包括ケア病床12床)・医療療養病床35床)にて医療福祉連携室室長と経営企画室を兼務。医療ソーシャルワーカー(MSW)として亀田総合病院で経験を積んだ後、医療課題は社会経済、経営、マーケティングの視点からも解決していく重要性を実感し、経営学修士(MBA)を取得。その他、医療経営士1級、介護福祉経営士1級などを取得し、講師業などにも取り組む。(過去のインタビュー記事)関連記事
- コロナ禍でも機能する地域連携の本質【ケース編】―病院経営ケーススタディvol.11
- 【看護・リハビリ・地域連携室編】地域包括ケア病床の専門職が持つべき“入口から出口”の意識―福井県坂井市立三国病院
- 生き残りをかけた営業活動〜医療連携機関の心を動かすための営業とは〜―病院マーケティング新時代(10)
【無料】病院経営事例集メールマガジンのご登録
病院長・事務長・採用担当者におすすめ
病院経営事例集メールマガジンでは、以下の情報をお届けします。
- 病院経営の参考になる情報
エムスリーグループのネットワークをいかし、医療機関とのコミュニケーションを通じて得た知見をお知らせします。 - セミナー情報
医師採用など、病院経営に役立つ知識が学べるセミナーを定期開催しています。