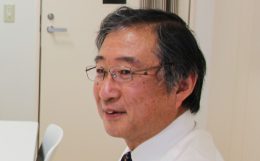兵庫県明石市に位置するふくやま病院(一般58床+緩和ケア30床)は、2016年の移転を機にスタッフが「また来てねと言える病院」をコンセプトにリニューアル。その設計に携わったのが、コミュニティデザイナーの山崎亮さん率いるstudio-Lです。地域住民も参加した病院づくりが大きな変化をもたらしたと語る山崎さん。コミュニティデザインの第一人者に、具体的な取り組みや効果について伺いました。
病院の青写真を描くのは、スタッフや住民
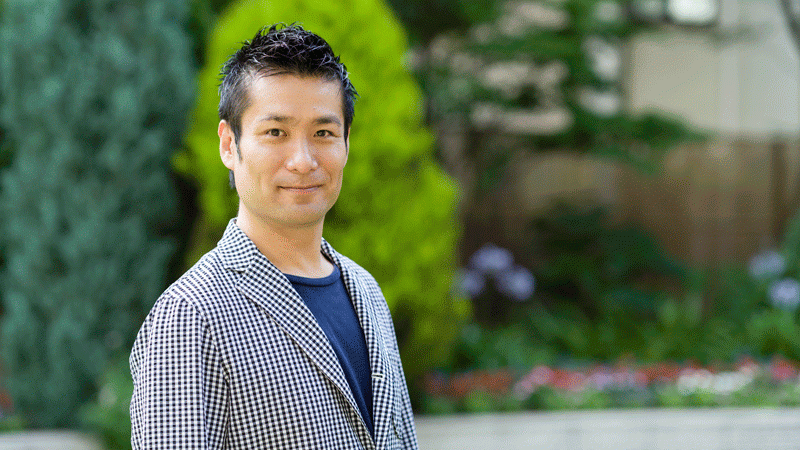
コミュニティデザイナー・社会福祉士 山崎亮氏
─山崎さんは、ふくやま病院のリニューアルをコンセプト作りから手がけました。そもそもコミュニティデザインは一般的な設計とどう異なるのでしょうか。
コミュニティデザインとは、一言であらわすなら“人と人とのつながりをデザインすること”です。私たちは、地域の課題をその地域に住む人々が主体的かつ持続的に解決していけるよう、デザインの力でお手伝いをしています。もともとは建築、つまりハードの設計を学んでいたのですが、「社会が抱えている様々な課題をものづくりだけでは解決できない」と気付いたのがきっかけです。問題解決のためにはハードとソフトの両輪が求められます。ところが、ソフト部分をデザインする人はまだ少ない。それなら自分でやってみよう、と思ったわけです。
─ふくやま病院リニューアルの経緯や取り組みの内容について教えてください。
まずは院長や副院長、事務長といった経営のコアメンバーでコンセプトを決めました。その際、「本音を言えば『また来てね』って言える病院にしたいんですよね」という発言があったんです。病院は病気になってから来るところだと思われているけれど、健康であるために行く病院、人々の生活とともにある病院があってもいいのではないか、と。様々な意見がありましたが、最終的にそのコンセプトでいこうということになりました。
次に約100名のスタッフと、コンセプトに基づきもう少し具体的な部分の枠決めを行いました。「自分たちはどう働きたいのか」「コミュニケーションのあり方はどう変わるのか」「ロゴマークやテーマカラー、制服、インテリアはどうするのか」…。意見を出し合うワークショップを実施して、集約したアイデアをひとつずつ図面に落とし込んでいきました。そうやってプロが作った設計図を、スタッフたちにどんどん変更してもらったんです。皆で家具を見に行ったりもしましたね。
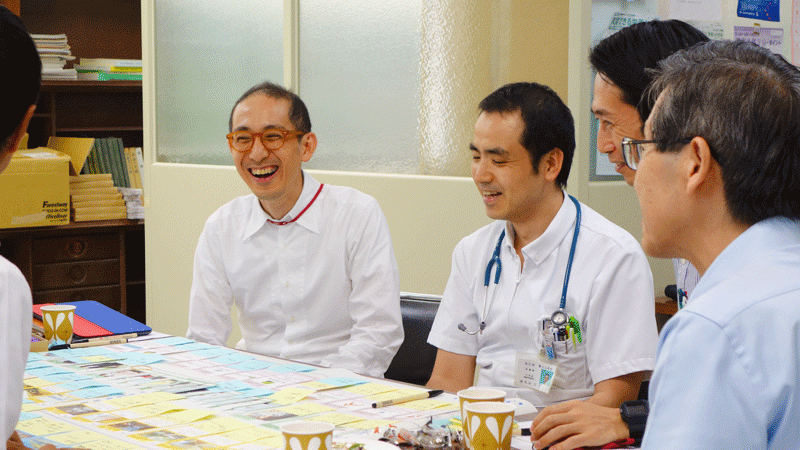
ふくやま病院のワークショップの様子
こうして院内のコンセンサスを得られた段階で、いよいよ地域住民へのヒアリングやワークショップです。まず1日24時間をどう過ごしているのかを100名くらいに聞き、地域の方々の“時間割”をおおよそ把握したところで、「空いている時間に病院のスペースを使ってどんなことをやりたいですか?」とアイデアを募集しました。地域の皆さんがやりたいことと病院がやりたいこと、両者が重なる部分を探して、実行に移していったんです。
たとえば、患者以外でも利用できるオープンな図書スペースは「入院時に本を読みたくても書店や図書館に行けない」「おすすめ本を共有できる場がほしい」といった声を受け実現しました。予算はクラウドファンディングで寄付を募り、まかないました。完成してからも寄付した方が来院したり、おすすめ本を持ってきてくれたりと新たなつながりが生まれています。他にも、実のなる木を植えたいという「食べられる庭」チームはせっせと苗を買ってきて世話をしてくれていますし、マルシェ(青空市)をやろうという人たちや病院のコミュニティホールでジャズライブを開催する人たちなど、各々病院を活用してくれています。病院を地域になじませていくには、地域の人達に入り込んでもらうのが一番なんです。病気じゃない人たちが病院で楽しそうに活動しているーー初動期に良い事例を見せて、「なんかおもしろそう」と興味をもってもらえれば成功です。
現場スタッフからの提案を引き出すには
──患者さん以外の住民が自由に出入りすることに、病院側の抵抗感はなかったのでしょうか。
最初は不安や自分たちの仕事が増える懸念もあったと思います。しかし、ワークショップなどを通じて病院を地域に”ひらく”ことの意義をしっかり理解すれば──つまり病院の課題を自分ごととして捉えることができれば、スタッフ自身がボトルネックを探り当てて解決策を導き出します。「そういうことなら、ここまでは出入り自由にしても問題ないのでは」などと、「どこまでひらくか」という前提で具体案が出てくるんです。その中から最適解を探せばいい。
注意したいのは、インプットなきところによきアウトプットは生まれない、という点です。「流行っているからワークショップやってみよう」と思いつきでスタッフを集めて漫然と話し合いをしても機能しません。ふくやま病院の場合も、まずはスタッフに対したとえば地域医療をめぐる状況や国内外の医療施設の先進事例など最新の情報をお伝えしました。そうすると、生活の中でも視点が少し変わる。たとえばニュースを見ても、「そういえばあの時、こういう話があったな。病院では何かできるのだろうか」と、頭の片隅にもやもやしたものが残っているんです。これを何回か繰り返してから意見を聞いてみると、「働いている彼らの実感」と「これからの時代の要素」がミックスされたアイデアが出てきます。わざわざそんな手間ひまをかけずとも、最新の情報や知見を持った専門家にお願いすればいいではないか、と思われる方もいるかもしれませんが、働いているスタッフ自身の中にこそ、経営コンサルタントや僕らのような部外者には決して考えつくことができないような発想が生まれるのです。
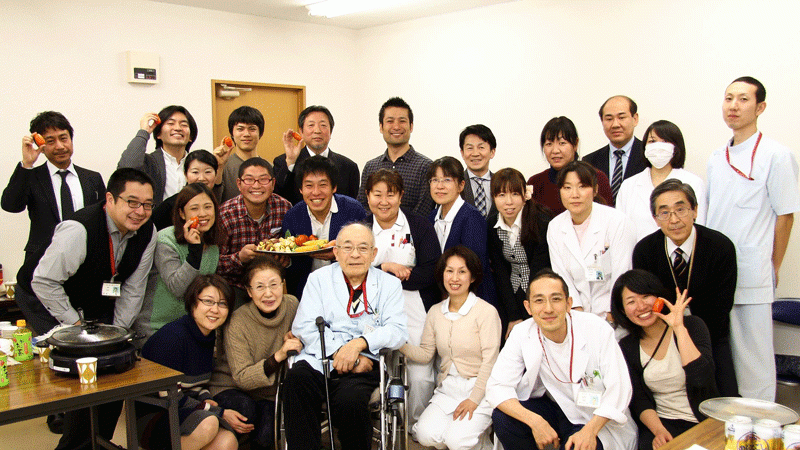
ふくやま病院の皆さんと山崎亮氏
病院を“まち化”することの効果とは
──病院づくりにコミュニティデザインの視点を取り入れることで、どのような効果があるのでしょうか。
患者さんにとって入院というのは非日常的な出来事です。外出もままならなければ、人と関わる機会も減り、一日中テレビを見るくらいしかすることがない…健康になるための入院なのに、入院生活が不健康につながってしまっているケースもあるのではないでしょうか。でも、病院が“まち化”されれば、患者さんも日常に近い生活を送ることができます。たとえば図書スペースで地域の人と一緒に本を読んだり、そこで世間話が生まれたり。ライブなど催し物が院内で開かれていれば、外出できない患者さんでも見に行くことができます。もちろんちょっと1人でいたい、という気分のときにはそうすればいい。そういった選択肢を持てること自体が患者さんにとって意味があると思います。
地域の人にとってもメリットがあります。まず、魅力的なスペースで自分たちのやりたい活動ができる。それに、いざ自分が病気になってしまっても、気心の知れたスタッフがいて、馴染みのある場所で診てもらえるのは大きな安心感につながります。親戚や家族が病気になったときも、自信をもって薦めることができるでしょう。結果的に、病院にとっては将来の集患にもつながるわけです。
おもしろいのは、病院づくりが医療機関の人材育成にもつながっている点です。病院スタッフは一連の経験を通して、自分たちでワークショップを実施できるようになります。リハビリ職や看護師の方々が複数の人たちの意見をうまくまとめられるようになったり、ワークショップを活発にするツールとしてカードゲームなどを自作したり…病院が完成した後も、自主的な活動につながっているそうです。その変化には目を見張るものがありますね。その他、一住民として知り合った人が来院すると、どんな趣味嗜好なのかを分かっているのでスタッフとしてはなにかとサポートしやすいという利点もあるようです。このように、建物をつくるだけでなく、建物を取り巻く人々にもたらす変化こそが、コミュニティデザインの目的とするところなのです。
2008年以降、日本の人口は減少の一途を辿っています。人口が減れば税収も減る。地方自治体の予算はどんどん縮小するでしょう。一方で、高齢化に伴い社会保障などへの支出は増加します。地方自治体の負担が増大する時代にあって、行政まかせでは地域の課題解決は困難です。しかも人口構造の変動は自治体によってばらつきがあるため、医療・介護のニーズに対しては地域ごとの取り組みが必要になってくる。言い換えれば、医療機関にも地域づくりの視点がより一層求められるということです。既に地域包括ケアシステムの中でそうした動向が見られますが、ふくやま病院のように、「いかに地域に根ざし、求められる存在になるか」という課題を抱えていることも少なくありません。コミュニティデザインの考えは、その解決のヒントになりうるのではないかと思っています。
<取材・文:角田歩樹>
studio-L代表。コミュニティデザイナー。社会福祉士。
1973年愛知県生まれ。大阪府立大学大学院および東京大学大学院修了。博士(工学)。建築・ランドスケープ設計事務所を経て、2005年にstudio-Lを設立。地域の課題を地域に住む人たちが解決するためのコミュニティデザインに携わる。まちづくりのワークショップ、住民参加型の総合計画づくり、市民参加型のパークマネジメントなどに関するプロジェクトが多い。