
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター医事管理課長/診療情報管理室長、国際医療福祉大学院 診療情報管理学修士。1987年、財団法人癌研究会附属病院に入職後、大学病院や民間病院グループを経て現職。その間、診療情報管理士、診療情報管理士指導者などを取得。現在、日本診療情報管理士会副会長、日本診療情報管理学会理事、医師事務作業補助者コース小委員会 委員長などを務める。
病院が最もよく取り扱う指標の一つに平均在院日数があります。今回は、この指標の活用方法について考えたいと思います。
筆者は、平均在院日数の変動を、 病院統計として ただ漠然と見るのではなく、医療マネジメントの視点から分析・活用することが重要であると感じています。たとえばDPCの効率性指数や「重症度、医療・看護必要度」などと関連付け、経営面への影響を見るということです。
また、平均在院日数は入院基本料の施設基準件の一つですが、計算の除外対象患者に関する記載が、2018年度の診療報酬改定で少し変更されました。計算上の大きな違いはありませんが、改めて確認しておきましょう。
計算対象外の患者に要注意!DPC病床の短手3に落とし穴
まず、今年度改定をふまえた注意点について。平均在院日数を計算する際、「短期滞在手術等基本料3(短手3)は対象患者から除外する」という条件自体に変更はありません。しかし改定に伴い、DPC算定病床ではこの短手3の手技がDPC包括請求対象に含まれることになったため、混同して平均在院日数の計算対象に含んで計算してしまう恐れがあります。したがって、改めて計算対象外とする手術等、すなわち「平均在院日数の計算対象としない患者」の選別が必要になっているのです。
具体的には、別表第2「平均在院日数の計算対象としない患者」の23(下記参照)が要注意。文中の「厚生労働省大臣が指定する病院」とは、DPC対象病院を指します。別表11の3にある手術等を実施し、入院後5日以内に退院した患者は、平均在院日数の計算から除外しましょう。
(省略)
23 診療報酬の算定方法第1号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院において、(中略)別表第11の3に規定する手術、検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
2つの平均在院日数
そもそも、医療現場で用いられる平均在院日数という指標には、2タイプがあることをご存知でしょうか。短手3等に関するものは、以下の【1】にあたります。
【2】各月の病床稼働状況を把握する、病院統計用のもの(院内用に【1】より簡素に計算)
平均在院日数の違いは、前述したような算定対象外患者の選別(電子カルテ上の設定)に関わります。ここをしっかり設定できていないと、両者が混在し、不正確な数値になっている可能性があります。電子カルテが導入されている医療機関の多くでは、【1】の計算を医事統計システムによって対応しています。そして対象外患者の設定は、人の手によって除外設定のコード登録を患者一人ひとり行うことが往々にしてあります。そこで、別表第2「平均在院日数の計算対象としない患者」を改めて確認しておきましょう。
平均在院日数など、施設基準で要件になっている数値は、言うまでもなく最も慎重に算出しなければならない部分です。誤って届け出ていることが適時調査などで発覚し、条件を満たせていなければ、莫大な返還金を求められるので注意しましょう。
医事課の分析力が問われる平均在院日数
さて、続いて病院統計に用いられる平均在院日数を考えてみましょう。こちらは病院経営管理上、特にポピュラーな指標で、病床稼働率と関連付けて分析する等、多くの医療機関で用いられています。ある意味、病院の経営実態を表す指標と言えるでしょう。その分、この数値が変動すれば、臨床現場の傾向や実態について説明が求められます。医事課は数値を追うだけでなく、シビアに原因を分析する必要があるということです。
たとえば、年末年始や5月の大型連休といった長期休暇の前月には、平均在院日数が短く出ます。これは、連休前後に一時的な入退院が増加し、計算式の分母「新入棟患者数 + 新退棟患者数」が増える等の理由からです。これを在院日数の短い患者が増えたからなどと分析するとミスリードになります(関連記事)。また、冬季に病床稼働率が上昇すると、平均在院日数が長くなる傾向も見られますが、これは循環器疾患や脳血管疾患、肺炎の患者の増加が原因として考えられます。このようなことを踏まえながら、原因分析を行わなければなりません。
その際に効果的なのが、DPCデータによる効率性指数(在院日数短縮の努力を評価する指標)の分析です。効率性指数の分析は、DPC分類ごとの標準的な在院日数と自院との比較になるので、客観的な状況把握・評価が可能です。
たとえば季節柄、患者数が減って病床稼働率が低下すると、近い日程でもベッドを確保しやすくなるので、「予定入院かつ短期入院」のできる疾患の比率が多くなる傾向にあります。平均在院日数は短縮するため、「病床が空いているのに、入院期間も短くしている」と勘違いする病院幹部も中にはいるでしょう。効率性指数を見せれば、疾患比率の変化に応じて平均在院日数が短縮したことを客観的に伝えることができます。
<編集:角田歩樹>
・【連載一覧】診療報酬請求最前線
・“病院の“働き方改革”はなぜ進まないのか?水島協同病院にみる、経営層がすべきこと
・公立図書館やマンション併設…機能分化が生んだ“変わり種”病院とは─建築家が語る病院の裏側
【無料】病院経営事例集メールマガジンのご登録
病院長・事務長・採用担当者におすすめ

病院経営事例集メールマガジンでは、以下の情報をお届けします。
- 病院経営の参考になる情報
エムスリーグループのネットワークをいかし、医療機関とのコミュニケーションを通じて得た知見をお知らせします。 - セミナー情報
医師採用など、病院経営に役立つ知識が学べるセミナーを定期開催しています。


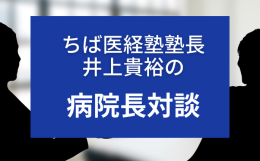
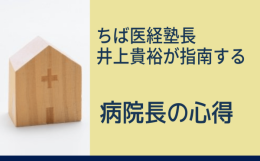


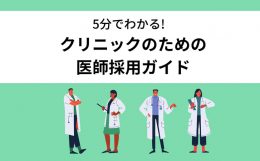
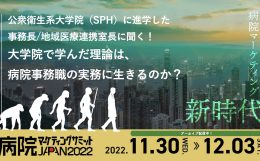



コメント